アニメ『東京喰種トーキョーグール』は、2014年に放送が始まって以来、原作の魅力を映像化した作品として注目を集めました。
一方で、その内容については「原作と違う」「作画がひどい」「意味がわからない」といった否定的な意見も後を絶ちません。
この記事では、アニメ『東京グール』シリーズがなぜ「ひどい」と評価されるのか、その理由を明確に整理しつつ、一方で評価されている点についても丁寧に紹介します。
初めて視聴する方も、すでに原作を読んだことがある方も、納得のいく形でこのアニメを再評価できるような内容を目指します。
東京グールのアニメはひどい?基本情報と評価
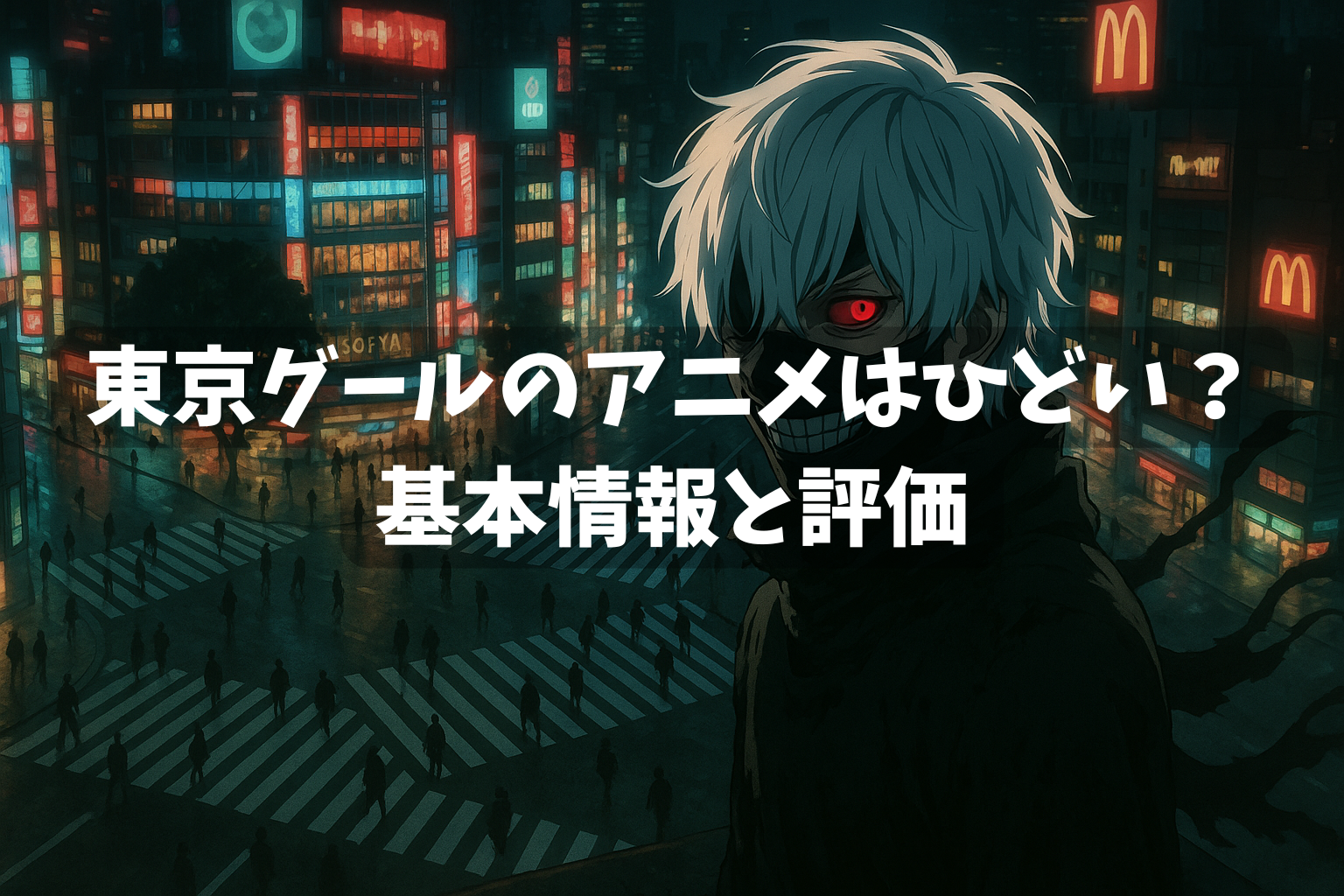
まずは『東京喰種』アニメについての基礎知識や、視聴者からの評価の傾向を整理しましょう。
あらすじ
東京には、人間とそっくりな見た目をしながら、人肉を喰うことでしか生きられない存在「喰種(グール)」が人知れず暮らしています。彼らは普通の人間と見分けがつかず、社会の影で静かに生活していますが、同時に人々にとっては恐怖の対象でもあります。
主人公・金木研(カネキ ケン)は、ごく普通の大学生で、文学を愛する穏やかな性格の持ち主でした。ある日、彼は本屋で知り合った女性・神代利世(リゼ)とデートをすることになります。しかし、その出会いは運命的なものでした。リゼの正体は喰種であり、カネキは命を狙われてしまいます。
リゼに襲われるカネキでしたが、突如リゼが鉄骨の落下事故に巻き込まれ死亡。その事故の際、重体となったカネキは病院に搬送され、緊急手術を受けることになります。命を救うために移植されたのは、なんとリゼの臓器。こうして彼は「半喰種」となってしまうのです。
人間でもなく、完全な喰種でもない自分の境遇に戸惑うカネキ。人間の食事を受けつけず、人肉を求める本能に苦しみながらも、自分の“人間性”を守ろうと必死にもがきます。そんな中で彼は喰種が集う喫茶店「あんていく」の人々と出会い、彼らとの交流を通して少しずつ自分の立場を受け入れていきます。
しかし、喰種と人間の対立は激化していき、カネキ自身も次第に戦いへと巻き込まれていきます。自分は何者なのか、人を喰わずして生きていくことができるのか——その苦悩と成長の物語が、『東京喰種』の根幹を成しています。
主な登場人物
- 金木研(CV:花江夏樹):本作の主人公。
穏やかな性格で文学好きの大学生だったが、喰種化をきっかけに性格や行動が大きく変化していく。序盤では弱々しく受動的だったが、仲間や敵との出会いを経て次第に内面が強化され、白髪化以降は冷静かつ戦略的な一面も見せるようになる。精神的な葛藤や苦悩が色濃く描かれる人物であり、物語を通して最も変化の大きいキャラクター。 - 霧嶋董香(CV:雨宮天):喫茶店「あんていく」で働く喰種の少女。
強気で口調が荒いが、根は仲間思いで非常に情に厚い。人間社会に溶け込みながらも、喰種としての生きづらさや差別に日々向き合っている。カネキとの関係は当初は対立的だったが、次第に信頼を築き、物語後半では重要なパートナーとなる。彼女の家族や過去にも物語上の深い背景がある。 - 月山習(CV:宮野真守):通称「美食家」と呼ばれる喰種。
美意識が極めて高く、食に対して強い執着を持つ。カネキに対して異常とも言える興味を示し、その存在を芸術的に“味わいたい”と考える変人。狂気的な行動が目立つが、彼の生い立ちや孤独感にも触れられ、シリーズを通して多面的な魅力を放つ。彼の演出は視聴者に強烈なインパクトを与える。 - 亜門鋼太朗(CV:小西克幸):喰種対策局(CCG)の若き捜査官で、強い正義感を持つ。
喰種に対して憎しみを抱きながらも、カネキや喫茶店「あんていく」の喰種たちと接する中で、「喰種にも人間と同じ感情があるのでは」と葛藤し始める。人間と喰種の間に立つ存在として、物語に深い問いを投げかけるキャラクター。戦闘能力にも優れており、主要なアクションシーンにも多く登場する。
アニメの概要
- 制作会社:studioぴえろ(『NARUTO』『BLEACH』などで知られる長寿アニメ制作会社。ダーク系やアクションに定評がある)
- 放送期間:
- 『東京喰種』:2014年7月〜9月(全12話)。原作第1巻〜第8巻あたりをベースに構成され、カネキの覚醒までが描かれる。
- 『東京喰種√A』:2015年1月〜3月(全12話)。原作と異なるオリジナル要素が多く含まれており、石田スイのネームを基にしたアニメオリジナル展開が大きな話題に。
- 『東京喰種:re』(第1期):2018年4月〜6月(全12話)。原作の続編シリーズをアニメ化したもので、佐々木琲世(カネキの別人格)を中心に新たな物語が始まる。
- 『東京喰種:re』(第2期):2018年10月〜12月(全12話)。物語のクライマックスを描くが、展開が急ぎすぎており、賛否両論の最終章となった。
- ジャンル:ダークファンタジー、アクション、サスペンス、心理ドラマ(人間と喰種という二項対立だけでなく、存在意義や自己認識など、深い哲学的テーマも含まれている)
原作との違い
『√A』は原作と異なる展開が中心となっており、視聴者の間では賛否が大きく分かれました。
石田スイ氏がアニメのネーム(脚本の原案)を提供したという点では原作者の意図が組み込まれているものの、アニメオリジナル展開によって重要なシーンや心情描写が大幅に変更されています。
特にカネキの心理の流れやアオギリの樹への加入理由が曖昧になっており、原作で丁寧に描かれていた変化が視聴者に伝わりづらいという問題があります。
『:re』に関しては、原作の後半部分を2クールで一気に消化してしまったため、ストーリーの密度が薄くなり、キャラクターの心理描写・人間関係の掘り下げが大幅に不足しています。
複雑な設定や多くの登場人物が入り乱れる中で、説明が省略されたり展開が急すぎたりすることで、「誰が何をしているのか分からない」と感じる視聴者も多く、物語への没入感が損なわれたという声が目立ちました。
評価:良いという意見
- 第1期の作画とOP「unravel」が神レベルで評価されている。特に戦闘シーンやカネキの覚醒の描写は、緊張感と美しさを兼ね備えており、多くの視聴者に衝撃を与えた。
- ダークな世界観と主人公の葛藤が深く共感される。カネキの「人間性を保とうとする苦しみ」や「自分が何者なのかを問い続ける姿」に、自分自身を重ねる視聴者も多く、特に若年層からの支持が厚い。
- 喰種という存在への社会的メッセージ性に感動した視聴者も多い。人と異なる存在が差別や迫害に直面しながらも生きようとする姿は、現実世界のマイノリティ問題とも通じる部分があり、作品の深みを感じさせる。
- 音楽、演出、キャストの演技のバランスが非常に良く、「アニメとしての完成度が高い」と評価する意見も多数見られる。特に花江夏樹さんの演技は「声でカネキの変化を表現しきっていた」と賞賛されている。
評価:悪いという意見
- 原作改変によりキャラクターの動機や心情が分かりにくい。原作では丁寧に描かれていたキャラの背景や関係性が、アニメ版では唐突な行動として描かれる場面が多く、感情移入しづらくなっている。
- 『√A』や『:re』での駆け足展開と説明不足により混乱する視聴者続出。特に『:re』後半は新キャラや専門用語が続々と登場する中、説明がないまま話が進むため、「気づいたら話が終わっていた」「置いてきぼり感がすごい」との意見が多く見られる。
- 特定エピソードの作画崩壊や、演出のブレが気になる。1期では安定していた作画が、シリーズが進むごとに品質がばらつき、視覚的な違和感を覚える視聴者も多かった。特に戦闘シーンでの迫力不足や作画崩れは作品の世界観を損なう要因となっている。
- 一部視聴者からは、「キャラの掘り下げ不足によりただのバトルアニメになっている」「感情の積み重ねが希薄」との厳しい指摘もあり、原作の深い心理描写が好きだったファンほど失望の声をあげている。
東京グールのアニメがひどい・意味わからないと感じる理由とアニメの魅力
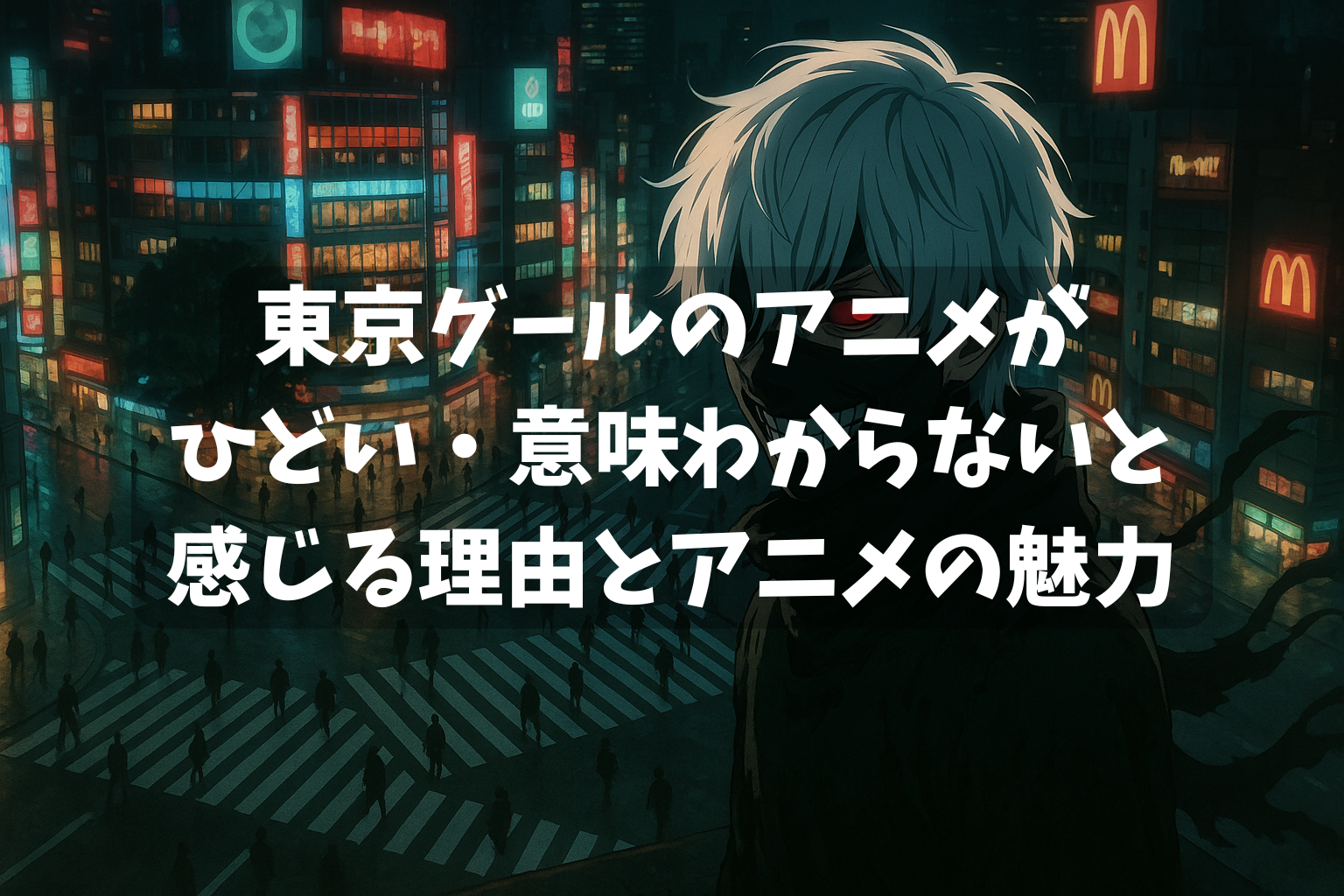
ここでは、東京グールのアニメが「ひどい」「意味がわからない」と言われてしまう理由を、具体的なシーンや構成の問題点とともに検証しつつ、作品が持つ魅力についても再評価します。
ひどい理由1:原作大改変
特に2期『√A』では、原作において丁寧に描かれていた登場人物たちの心理描写や関係性の変化が、大幅にカットされたり、描かれ方が変更されたりしています。
その結果、初見の視聴者には物語の流れがつかみにくくなり、「なぜこのキャラがこう動いたのか?」「何を目的にしているのか?」といった疑問を感じやすくなっています。
たとえば、カネキがアオギリの樹に加入するという展開は、原作では心の葛藤と喰種としての自覚の芽生えを経た上での選択として描かれていました。
しかしアニメではその過程が省略されており、カネキの行動が唐突で説得力に欠けるように見えてしまいます。
また、原作ファンが特に重要視していた“カネキの精神的変化”や“仲間との絆”といったエピソードが削除・改変されたために、視聴者がキャラクターに感情移入しづらくなっています。
カネキの苦悩や決断に至るプロセスが描かれないことで、視聴者に「共感」ではなく「置いてけぼり感」を与えてしまったのです。
一部の視聴者からは「これは別作品だと思って観た方がいい」「原作を読んでいないと理解できない構成」という意見も多く見られ、原作改変による違和感は東京グールアニメ全体に大きな影響を与えたといえます。
ひどい理由2:作画
1期では比較的安定していた作画も、2期以降になると全体的なクオリティにばらつきが出始めました。
特にキャラクターデザインに関しては、表情の描き込みや動きの滑らかさに欠けるシーンが増え、視聴者の間で「手抜き」「省エネ作画」といった声が目立つようになりました。
背景描写についても、1期では街並みや喫茶店「あんていく」の空気感などが丁寧に描写されていましたが、2期以降は色彩や奥行きの表現が簡略化され、物語の雰囲気に没入しにくくなったという意見が多くあります。
とくに『:re』2期では、戦闘シーンにおいてエフェクトの演出が簡素で、動きが機械的かつ単調になってしまっている点が問題視されました。
スピード感や迫力が伝わりづらく、喰種同士の激しい戦闘のはずが、画面上では緊張感がまったく感じられないという評価もあります。
さらに、カットインや表情のアップなどの演出技法も限られたパターンで繰り返されており、「予算や制作スケジュールの厳しさが作画に影響しているのでは」と疑う声すらありました。
こうした要素が重なり、アクションやドラマを支えるはずの作画が、逆に作品の魅力を損ねる結果となってしまったのです。
ひどい理由3:アニメオリジナル
原作に忠実でないアニメオリジナル展開が多く盛り込まれていることで、特に原作を読んでいない視聴者にとっては物語の背景やキャラクターの心情が伝わりづらく、意味が通じにくくなってしまっています。
特に2期『√A』では、原作者・石田スイがネームを提供していたにもかかわらず、原作の重要な展開や伏線をスキップし、独自の展開を優先させたことで、視聴者の理解や感情の流れが途切れてしまったという声が多く見られました。
例:ヒデとの別れや再会に至るまでの感情の積み重ねや背景描写が非常に希薄で、再会シーン自体は印象的であるものの、その感動が積み上げられていないため「泣けない」「唐突だった」といった反応を呼びました。
また、他のキャラクターとの関係性にも矛盾や唐突さが生まれ、原作を読んでいる視聴者からも「展開の意味が伝わらない」「原作を知っていないと全体が理解不能」といった不満が目立ちました。
ひどい理由4:キャラの掘り下げ不足
滝澤政道、瓜江久生、鈴屋什造といった人気キャラクターが多数登場する『:re』編では、物語の進行が非常に早く、各キャラに対する丁寧な描写やエピソードの積み上げが十分に行われていない点が大きな問題として挙げられます。
本来であればそれぞれが抱えるトラウマや背景、信念といった内面の掘り下げがあってこそ、彼らの行動や選択に説得力が生まれるはずですが、アニメではそうした心情描写が省略されることが多く、ただ表面的なセリフとアクションだけでストーリーが進んでしまっているのです。
例えば滝澤政道は、喰種化した過程や人間時代とのギャップが極めてドラマティックなキャラクターですが、アニメではその苦悩や揺れ動く感情の機微が省略され、単なる暴走キャラのように扱われています。
また瓜江久生は上司としての成長や仲間との関係に大きな変化があるにもかかわらず、その過程がしっかりと描かれず、キャラの魅力が伝わりきらないまま進行してしまいました。
鈴屋什造もまた、原作では過去の境遇や内面の変化を通じて多くのファンを魅了しましたが、アニメでは彼の成長プロセスが短くまとめられたことで「ただ出てきて戦って退場するだけ」といった印象を与えてしまう結果となっています。
こうした掘り下げ不足により、キャラクターの存在感が薄まり、結果として視聴者が感情移入しにくくなり、物語全体の厚みを損なってしまった点が大きな欠点とされています。
魅力1:アニメ1期だけは楽しめる
アニメ『東京喰種』の第1期は、原作の前半部分を比較的忠実に描いており、シリーズ全体の中でも特に高い評価を受けています。
中でもカネキが拷問を受けて覚醒するシーン(通称「白カネキ覚醒」)は、心理描写・BGM・映像演出が見事に融合し、視聴者の記憶に強く残る名場面として語り継がれています。
このシーンでは、カネキの精神が崩壊しつつも、自分の中にある人間性と喰種としての本能との間で揺れ動く様子が、内面のモノローグや過去の記憶を交えながら丁寧に描かれています。
拷問シーンの残酷さと、その中で「自分を守る」という決意に至るカネキの変化は、視聴者に強い感情を与える要因となりました。
さらに、白髪に変化するビジュアル的な演出や、音楽「unravel」の使い方も相まって、視覚・聴覚ともにインパクトのある演出が光ります。
例:「僕はもう、誰も傷つけたくない」と語るシーンは、第1期の象徴とも言える名ゼリフであり、カネキというキャラクターの核心を示す重要な一言として、多くのファンにとって忘れがたい瞬間となっています。
魅力2:声優と音楽のクオリティ
花江夏樹さんの繊細で迫真の演技は、カネキの心の葛藤や変化をリアルに表現しており、作品に深みを与えています。
特に、感情が揺れる場面やカネキの覚醒時の声のトーンの変化には、多くの視聴者が引き込まれました。彼の演技は、視聴者にカネキの痛みや決意を直感的に伝える力を持っています。
OP「unravel」(TK from 凛として時雨)は、作品のテーマやカネキの苦悩を見事に表現した楽曲であり、アニメファンの間でも「神OP」として高く評価されています。
イントロの切なさと、サビにかけての力強さが、物語の世界観や登場人物の内面を鮮やかに彩っています。
また、ED楽曲もその時々のエピソードに応じた感情の余韻を巧みに演出しており、視聴後の印象をより深く残す仕上がりとなっています。
劇伴音楽(BGM)も、緊張感のある戦闘シーンから、しっとりとした感情描写の場面まで幅広く活躍しており、各シーンに必要な緊張感や哀愁、焦燥感などを的確に演出しています。
BGMの使いどころが非常に巧妙で、作品全体の没入感を高める重要な要素となっています。
魅力3:深いテーマ性と共感ポイント
“喰種=異質な存在”を通じて描かれる差別、恐怖、アイデンティティの問題は、本作の最大の魅力の一つです。
喰種という存在は、人間とほぼ変わらない外見を持ちながら、食料として人肉を必要とするという点で明確に“異質”とされ、社会から排除され、迫害を受けています。
その姿は、現実世界におけるマイノリティの立場や異文化への偏見、差別のメタファーとして強く機能しています。
主人公・カネキは、事故をきっかけに自らが喰種となってしまい、それまで「敵」としていた存在の視点から世界を見ることになります。
「人間でありたい」と願う一方で、「喰種として生きなければ死ぬ」という現実の中で、自らのアイデンティティが揺れ動き、苦しみ続けるのです。
このような設定の中で描かれる葛藤は、多くの視聴者にとって他人事ではありません。
自分の中の“正しさ”と“本能”、社会からの評価と本当の自分とのギャップ、自分が本当に属すべき場所とは何か——そうした普遍的なテーマが、カネキというキャラクターを通して深く描かれているのです。
視聴者の中には、学校や家庭、職場などで「周囲に適応するために自分を偽っている」と感じている人も多く、カネキの葛藤や決断に心から共感したという声が少なくありません。
だからこそ、「人間でいたい」「でも生きるために喰わねばならない」という矛盾した内面の叫びが、多くの人の心を強く打つのです。
総括:ポイント
- 原作ファンにとってはアニメの改変・カットが致命的な要因に。重要なシーンやキャラクターの心理描写が省略されており、原作を愛する視聴者ほど失望の声が大きくなっている。
- 一方で、1期の演出・演技・音楽の完成度は今も高評価を得ており、アニメ単体でも十分に楽しめるクオリティの高さがある。
- アニメから入った人には「意味が分からない」「説明不足」「キャラの背景が浅い」となる要素が多く、原作未読者にとってはつまずきやすい作品でもある。
- 『東京喰種』は、アニメ単体では評価が分かれるが、原作とセットで見ることで物語の流れやキャラの心情が補完され、理解と感動が深まりやすい。
- 本作はエンタメ作品としての側面だけでなく、アイデンティティや差別、社会への適応といった深いテーマを内包しているため、多様な解釈が可能であり、それが作品の魅力にもなっている。
アニメ『東京グール』は、視聴者によってその受け止め方が大きく異なる、いわゆる“評価が割れる作品”の代表例といえるでしょう。
ただし、それは決して悪いことではなく、それだけ多くの感情や意見を引き出すだけの力を持った作品である証拠でもあります。
自分にとってこの作品がどう映るのか、それを確かめるためにも、まずはアニメ1期から視聴してみることをおすすめします。
そして興味を持ったら、ぜひ原作コミックスにも触れてみてください。アニメと原作を通じて、『東京喰種』という世界の奥深さをより深く味わうことができるはずです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
アニメ・映画が大好きで毎日色んな作品を見ています。その中で自分が良い!と思った作品を多くの人に見てもらいたいです。そのために、その作品のどこが面白いのか、レビューや考察などの記事を書いています。
詳しくはこちら




コメント