みなさんは「製作委員会方式」という言葉を聞いたことはありますか?
「製作委員会方式」という言葉は、主にアニメ業界で聞く言葉だと思いますが、ちょっとマニアックな言葉でもあると思います。
それで、製作委員会方式がなんなのかわかる!という方は「製作委員会方式じゃないアニメ」ってあるの?という疑問もあると思います。
今回は主に「製作委員会方式じゃないアニメ」について解説していきたいと思います。
「製作委員会方式」ってなんだ?って思った人、大丈夫。
ここでは、アニメの裏側を知らなくてもスッと理解できるように、例え話や雑談も交えながら説明していきたいと思います!
製作委員会方式とは?ざっくり解説

さて、まず「製作委員会方式」っていう言葉から解説していきたいと思います。
これは、ざっくり言うと「みんなでお金を出し合ってアニメを作るスタイル」のことです。
アニメは、制作するのにとーってもお金がかかります。
だから、出版社、テレビ局、広告代理店、音楽レーベル、玩具メーカー……といったようないろんな会社が集まって、「じゃあ、このアニメを一緒に作ろう!」というふうに手を組みます。
これが「製作委員会」です。
リスクも分散されますし、グッズや配信でも収益が見込めるし、業界的には安定したビジネスモデルなんです。
なので、「〇〇製作委員会」というクレジットが各アニメのオープニングやエンディングに入っているのをみたことがある人も多いのではないでしょうか。
あれは、お金を共同で出す会社や団体をまとめた言い方だったのです。
しかし…!
この方式にはちょっとした“制約”もあります。
例えば、製作委員会に入っている組織、みんなの意見を聞かないといけないですので、ちょっと尖った表現は難しいことが多いです。
それに、話題になってても、2期が作られないこともあります。
そういった、製作委員会方式のメリット・デメリットの詳しい説明については後で行います。
では、逆に“製作委員会じゃない”アニメって何?という疑問について解説していきたいと思います。
製作委員会方式じゃないアニメってどんなの?
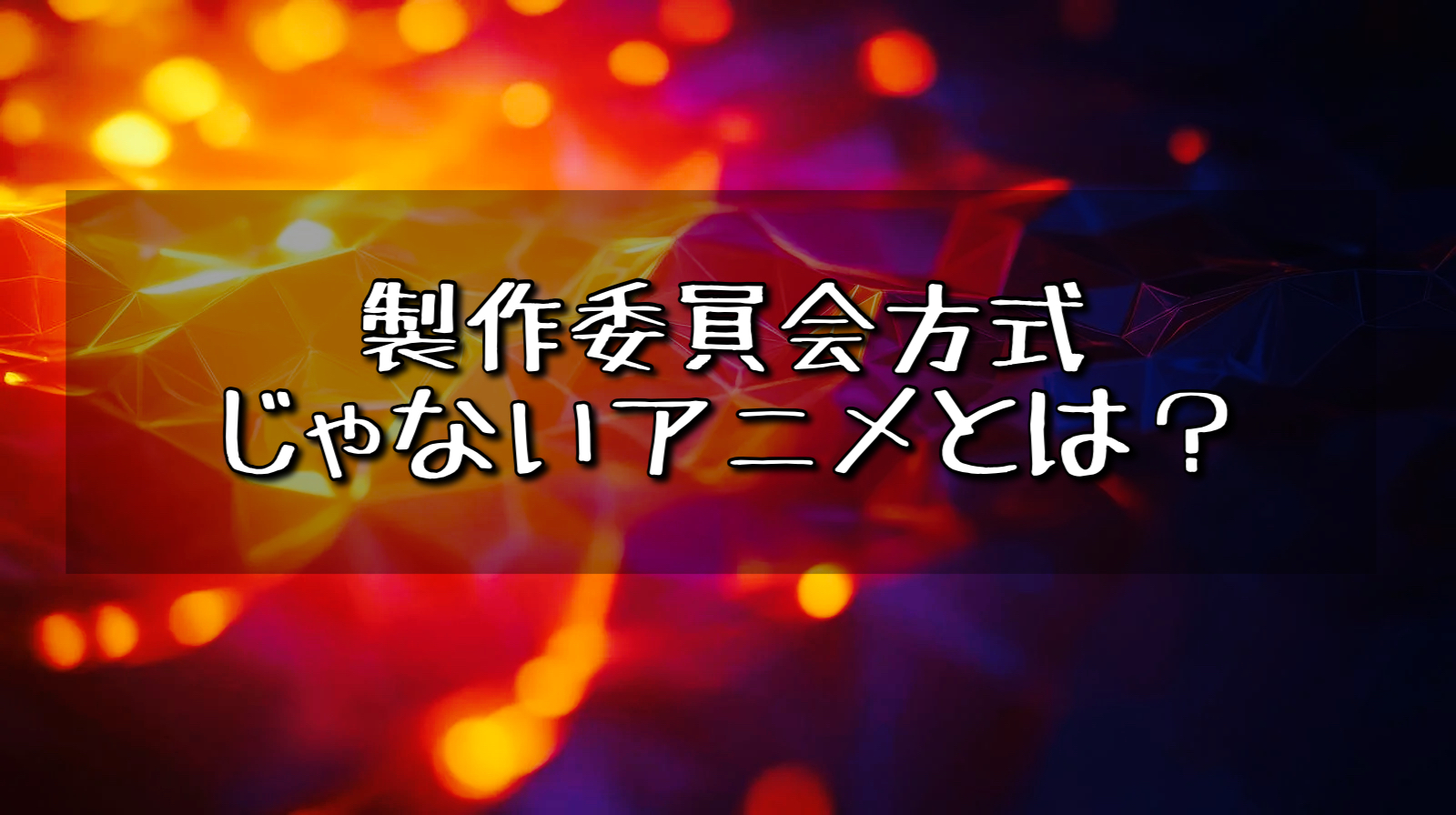
「製作委員会方式じゃないアニメ」は、簡単にいうと、単独で作ってるアニメのことです!
つまり、「うちの会社(あるいは一人)だけで作っちゃう!」ってスタイルになります。
特に「製作委員会方式じゃないアニメ」の中で、わかりやすく数が多いのが、劇場アニメです。
製作委員会方式じゃない劇場アニメ
この方式の代表例が、庵野秀明監督の『シン・エヴァンゲリオン劇場版』や、新海誠監督の『君の名は。』などです。
例えば『君の名は。』は、東宝がほぼ単独出資で作ってて、「製作委員会」の形式ではなかったんです。
だからこそ、新海誠監督の世界観や演出がブレずに完成された作品になったと考えられます。
また、スタジオジブリ作品も同様です。
宮崎駿監督が自由に作れるように、製作委員会を使っていません。
ただ、これはとても大変なことです。
アニメ一本作るのに何億円ってかかる世界です!
だから、よほどの信頼や実績がないとこの方式では難しいのが現実です。
すなわち、新海誠や庵野秀明、宮崎駿などの有名監督をもつスタジオは、個人名×ブランドで集客可能なため、大規模な製作委員会に頼らずに済むのです。
以下、劇場アニメで製作委員会方式じゃないものをまとめてみました。
| タイトル | 制作スタイル | 補足 |
|---|---|---|
| 君の名は。 | 東宝単独出資 | 新海誠ワールドが炸裂! |
| 天気の子 | 同上 | 世界観にこだわりまくり! |
| すずめの戸締まり | 東宝単独出資 | 社会的テーマも扱う話題作 |
| シン・エヴァンゲリオン劇場版 | カラー(庵野秀明)主導 | 職人魂の結晶! |
| 千と千尋の神隠し | ジブリ単独 | あの世界観、納得の自由度! |
| 風立ちぬ | 同上 | 宮崎駿監督がやりたい放題(いい意味で)! |
| もののけ姫 | 同上 | 壮大な自然×人間ドラマ |
| 崖の上のポニョ | 同上 | 子ども向けでも表現の自由満載 |
| 火垂るの墓 | ジブリ&徳間書店主導 | 社会派アニメの代表格 |
| この世界の片隅に | クラウドファンディング型 | ファン出資型の新モデル! |
どれも有名作がかりですね。
クリエイターの個性がビシバシ伝わってくる作品ばかりです。
製作委員会方式じゃないテレビアニメ
劇場アニメでは製作委員会方式ではないアニメは割と普通のことですが、テレビアニメではどうでしょうか。
みなさんが知っているようなテレビアニメでも、だいたい2つくらいに分類されて製作委員会方式とそうでないものが存在します。
それが、超有名作か、それ以外かです。
ここでいう超有名作とは、『ドラえもん』『名探偵コナン』『クレヨンしんちゃん』などの朝や夕方の枠で放送されているような作品です。
これらのアニメは製作委員会方式じゃないアニメ、または、それに準ずる製作方式をとっているアニメです。
それで、超有名作ではない作品の中にも、製作委員会方式じゃないアニメがありますので紹介していきます。
有名なのは、『ポプテピピック』という作品でしょうね。
テレビアニメ『ポプテピピック』は製作委員会方式ではなく、キングレコードが単独で出資・製作を行いました。
| タイトル | 概要・補足 |
|---|---|
| 『けものフレンズ(第1期)』 | テレビ東京などが主導。実質的に製作委員会形式を取らなかったことで有名。 → 爆発的人気とともにクリエイター側との摩擦も話題に。2期があんなことに。。。 |
| 『アニメガタリズ』 | DMM.futureworksが主導し、自社でのリスクテイクを重視。 → 完全に委員会外資本で制作された。 |
| 『チェンソーマン』 | 製作委員会を使わず、MAPPA単独出資。 → 高品質・作家性重視の挑戦として業界内外から注目。 |
このようにテレビアニメで製作委員会方式をとっているアニメは、劇場アニメと比べて有名どころでも少ない数しか製作委員会方式をとっていないです。
ではなぜ、製作委員会方式のアニメがほとんどなのか。
その理由を解説するために、製作委員会方式のメリット・デメリットを解説していきたいと思います。
製作委員会方式のメリット・デメリット
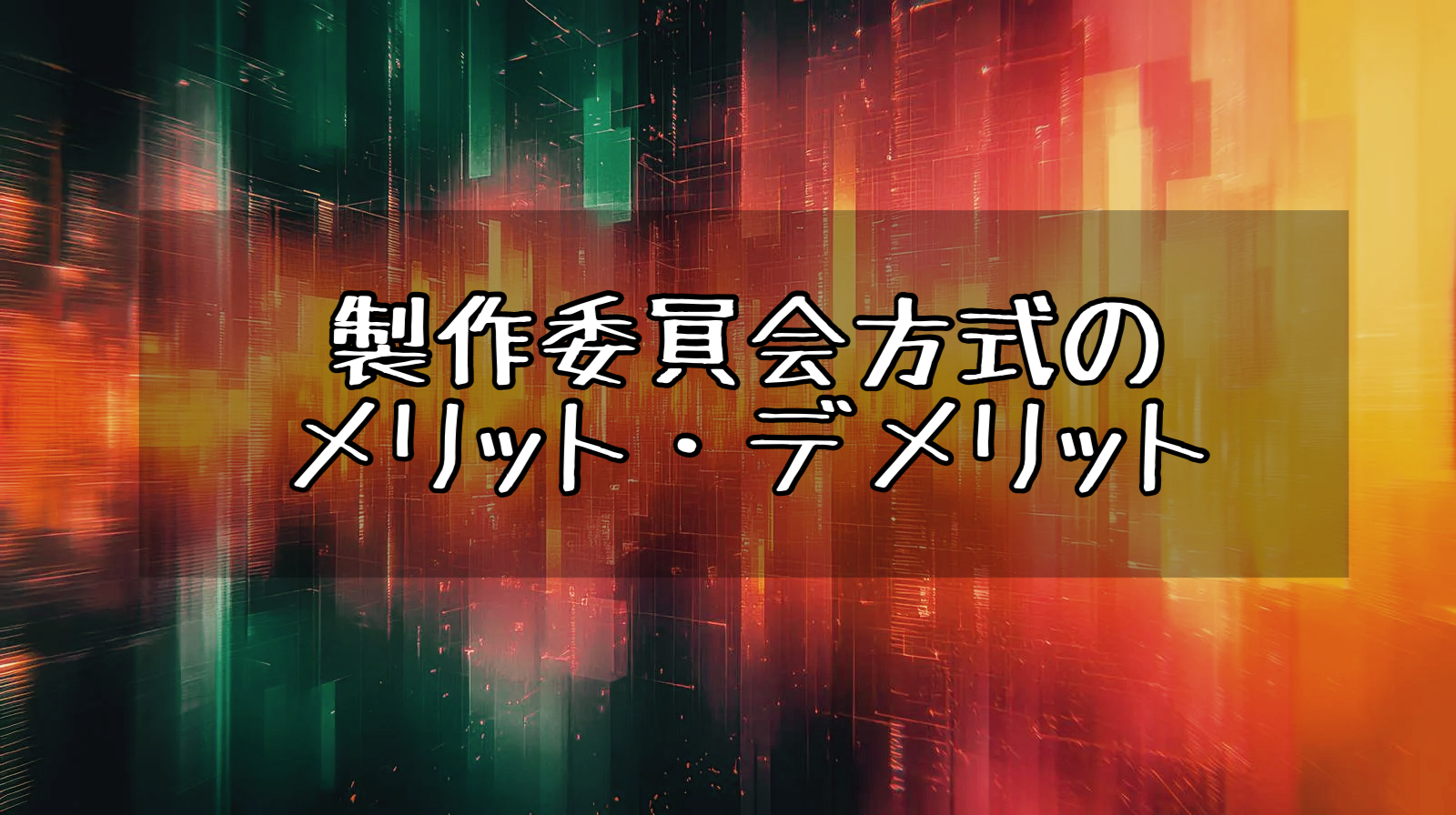
以下製作委員会方式のメリットとデメリットをまとめました。
メリット
| メリット | 説明 |
|---|---|
| ① リスク分散 | 一社だけでなく複数企業で出資するため、失敗時のリスクが小さくなる。 |
| ② 資金調達しやすい | 音楽・出版・配信など複数の収益源から資金を得やすく、制作費を確保できる。 |
| ③ 多様なプロモーションが可能 | 各社が自社メディアで宣伝を行える(例:テレビ局・雑誌・YouTubeなど)。 |
| ④ 各分野のプロフェッショナルが参加 | 出版社・音楽会社・配信会社などが参加し、幅広いノウハウが活用される。 |
| ⑤ 商業的に成功しやすい体制 | 一定のヒットを見込んで企画されるため、マーケティングも手厚い。 |
上記が製作委員会方式の大まかなメリットになります。
ここから見えてくるのは、超有名作品と比べてブランド力に乏しいアニメは、製作委員会方式で製作しないと、そもそもアニメ自体が製作されない可能性があると思います。
毎週毎週様々な深夜アニメが放送され、私たちは大量のアニメを見ることができていますが、このように大量に見ることができるようになっているのは、製作委員会方式でアニメを作っているためと言えるでしょう。
「この漫画やラノベ、アニメ化してほしいけどマイナーだな〜」という作品がアニメ化されるのは、製作委員会方式のおかげな訳です。
デメリット
| デメリット | 説明 |
|---|---|
| ① クリエイティブの自由度が下がる | 出資者の意向が反映されやすく、作家性や挑戦的表現が制限されることがある。 |
| ② 収益が分散されすぎる | 出資比率に応じて分配されるため、制作会社やクリエイターには利益がほとんど入らないことも。 |
| ③ 意思決定に時間がかかる | 多数の企業が関わるため、調整や承認に時間がかかり、スピード感に欠ける。 |
| ④ 企画が保守的になりやすい | 投資リスクを抑えようとするため、既存IPや流行に偏った作品が増える傾向。 |
| ⑤ 制作会社に収益が還元されにくい | 製作委員会が立ち上がった際に、より安価に製作できるアニメ制作会社が選ばれるため、アニメ制作会社が損をするような仕組みでもある。 |
上記が製作委員会方式のデメリットになります。
よく皆さんが耳にするのは、「クリエイティブの自由度が下がる」ことと、「制作会社に収益が還元されにくい」ということだと思います。
「クリエイティブの自由度が下がる」というのは、多くの会社が絡むことで、アニメ制作会社が派手な挑戦をしにくいということです。
扇動多くして船山に登るという言葉のような状態です。
「制作会社に収益が還元されにくい」というのは、これも大きな問題で、製作委員会方式は資金調達がしやすいというメリットがある一方で、製作委員会側がアニメ制作会社を選ぶ権限を持つ場合が多いため、アニメ制作会社不利の方式とも言えるわけです。
ですので、アニメ制作会社としては、資金があれば、自分たち単独でアニメーションを作りたいのは山々なんでしょうが、現実的には製作委員会方式でやらざるを得ない状況なのかなと考えられます。
製作委員会方式じゃないアニメのメリット・デメリット

製作委員会方式アニメのメリット・デメリットを裏返せば、製作委員会方式じゃないアニメのメリット・デメリットになると思いますので、まとめてみました。
★メリット
- 表現の自由度が高い:企業の意向に左右されにくいから、作家性が前面に出る。
- クリエイターの意図が通りやすい:監督や脚本家のビジョンを実現しやすい。
- 収益が集中する:当たれば、その制作会社がほとんどの利益を得られる!
こういったメリットがあるにしろ、結局外れれば、不利益を一緒くたに食らうため、現実的ではない方式なのでしょうね。
☆デメリット
- 資金リスクが高い:全部自前で出すから、コケたらヤバい。
- 宣伝が弱くなりがち:製作委員会と違って広告連携がしにくい。
- 続編の判断も一社で決める:ヒットしても、次作が作られるかはその会社次第!
何かしらの作品を製作する際に、一番ネックになるのはやはり、資金面です。
私もプロには到底及びませんが、数十人規模の作品制作に携わったことがありますので、資金調達とその資金内でやりくりする大変さは少なからずわかっているつもりです。
私は実写しかやったことがありませんが、どこかに力を入れると、どこかが杜撰になってしまうというジレンマはいつも抱えています。
それで、大胆な挑戦はできないが、資金面で問題なく制作できる製作委員会方式というものがあれば、それが安牌として、スタンダードな作り方になるのは、当然のことであると思います。
製作委員会方式じゃない=応援の意味も強い
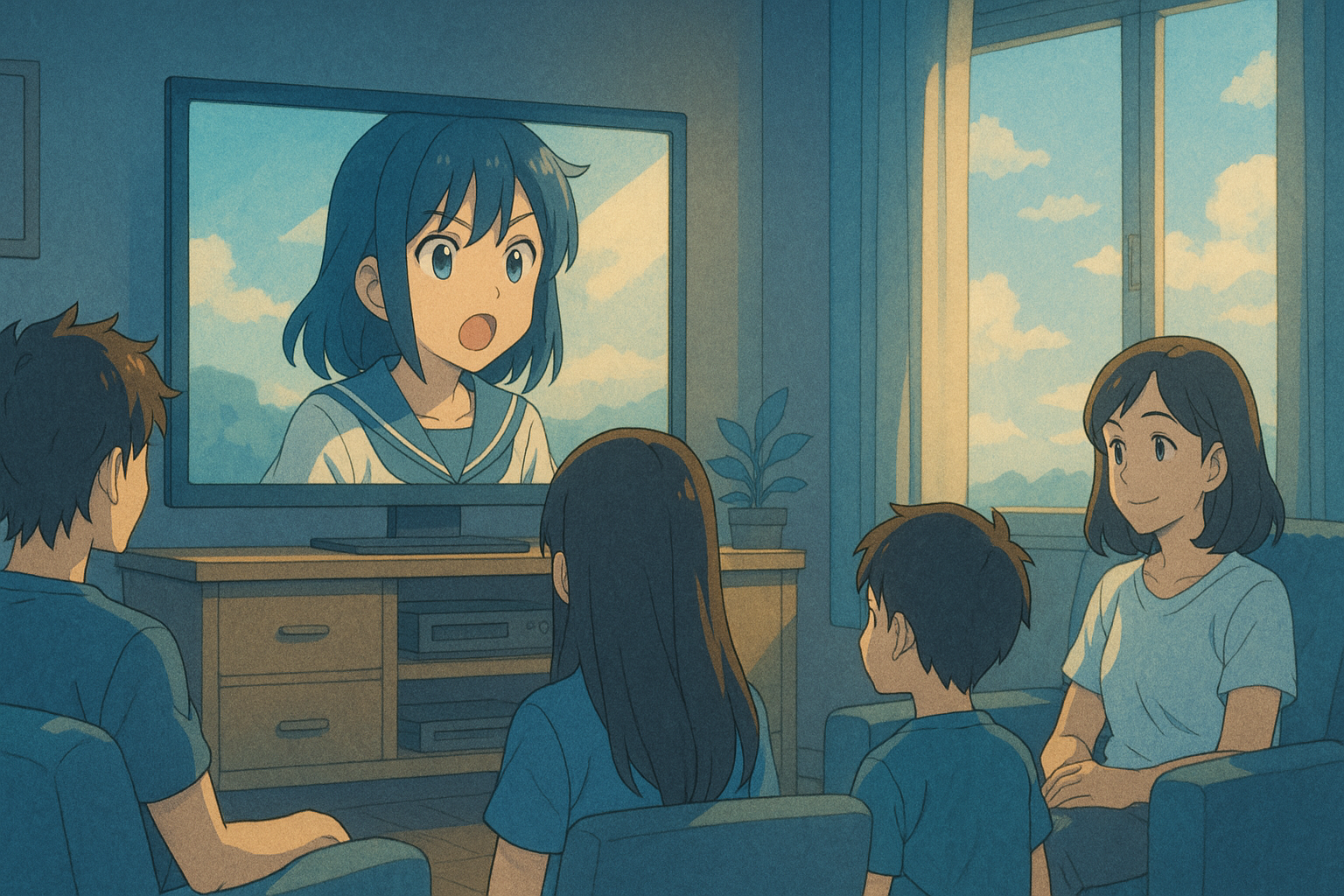
実は、こういった作品を観るってこと自体が、作り手への応援になると思います。
たとえば『この世界の片隅に』は、最初クラウドファンディングから始まって、多くの人の支援があって完成しました。
だからこそ、映画館で観ることも、Blu-rayを買うことも、すべてがクリエイターの支えになっていく。
製作委員会型だと収益が分散されるけど、単独出資型だと、売れたぶんだけ直接そのクリエイターや会社に還元されることが多いのは、重ね重ねいっていることです。
つまり、作品を応援=作り手を応援ってことになります!
今後の動き:ネット配信と個人制作の時代へ?
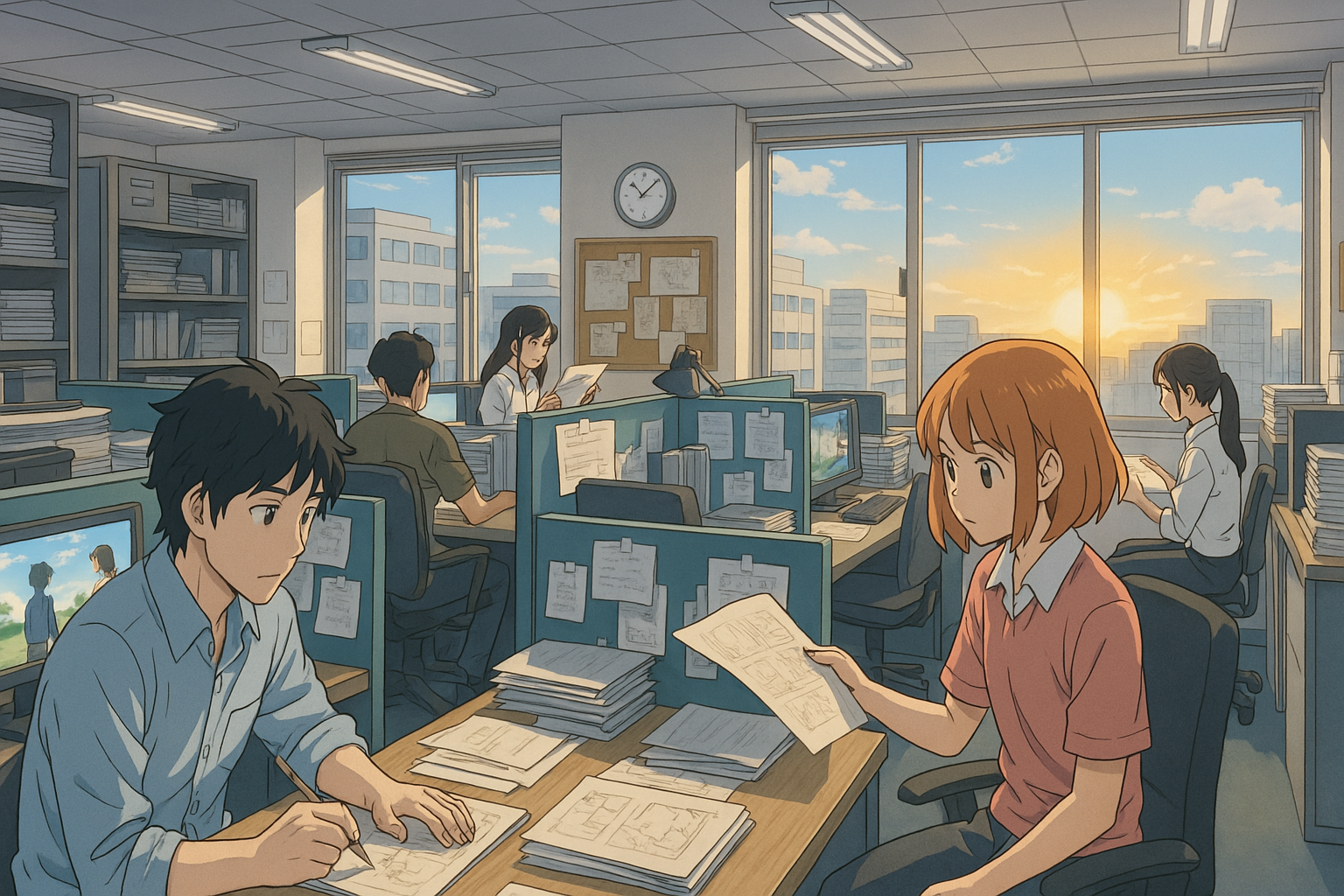
最近は、NetflixやAmazonなどがアニメに直接出資してるケースも増えています。
これも実は、製作委員会方式じゃない例の一つです。
Netflixオリジナルで配信されてる『エデン』や『Yasuke』なんかもそうですし、YouTubeで発表された自主制作アニメが話題になることもあります。
つまりこれからは、製作委員会じゃないアニメの選択肢がどんどん広がっていく時代になるかもしれませんね。
まとめ:アニメの裏側も“物語”の一部
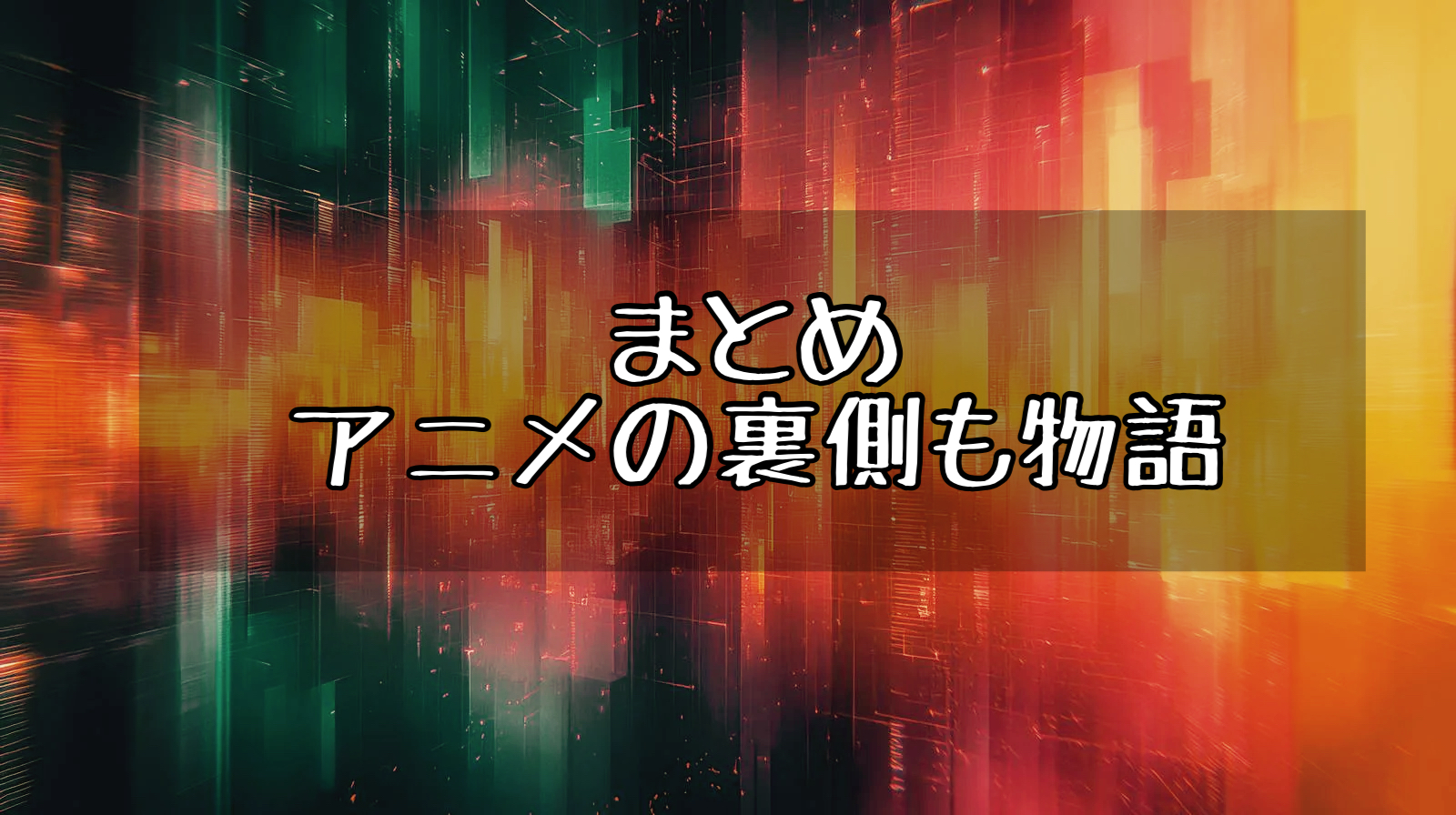
さて、長くなりましたが、今日のまとめです!
- 製作委員会方式は業界標準だけど、自由度には限界あり
- 製作委員会方式じゃないアニメは、作家性が高く、挑戦的な作品が多い
- ファンの応援が、作品と作り手をダイレクトに支える仕組み!
- ネット配信時代で、個人や少人数でもチャンスが広がってきている
アニメは、絵や声だけじゃなくて、作り方にもストーリーがあります!
作品の奥深さを知りたい人は、ぜひこの“制作方式”にも注目してみてください!
最後まで読んでくれてありがとうございます。
アニメ・映画が大好きで毎日色んな作品を見ています。その中で自分が良い!と思った作品を多くの人に見てもらいたいです。そのために、その作品のどこが面白いのか、レビューや考察などの記事を書いています。
詳しくはこちら

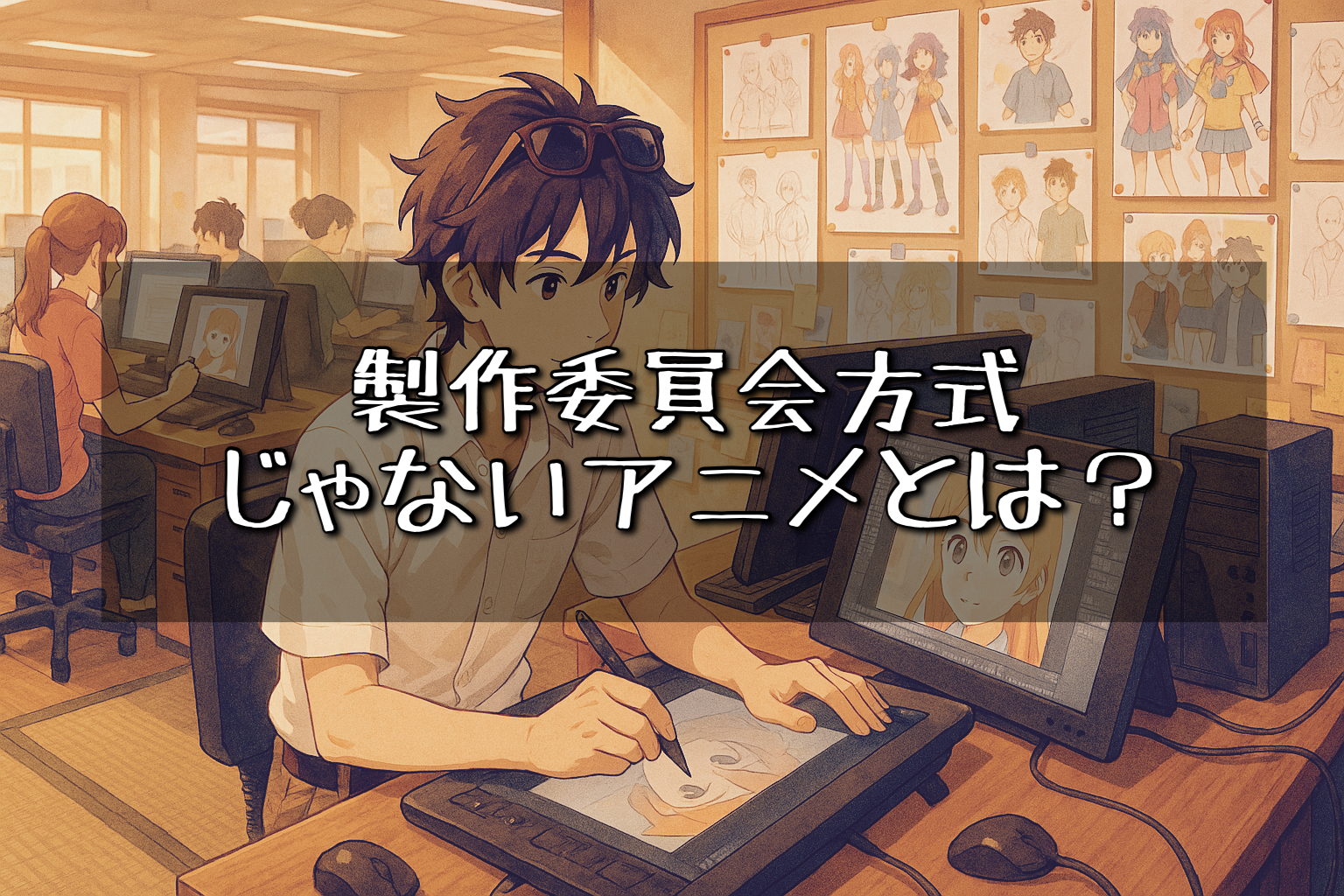



コメント