SNSや掲示板で「ニセモノの錬金術師って打ち切りになったの?」という声を見かけるようになりました。
結論から言えば――『ニセモノの錬金術師』は打ち切りではありません。
むしろ、pixiv発のラフ版が完結を迎え、商業版がその続きを丁寧に描いている、いわば“第2の章”に突入している状態です。
この記事では、なぜ打ち切り説が出たのか、原作と商業版の違い、そして今後の展開予想まで、読者目線でわかりやすく解説します。
『ニセモノの錬金術師』打ち切りの噂は本当?
最近、「ニセモノの錬金術師って打ち切りになったの?」という声をSNSで見かけるようになりました。
話題になっている理由にはいくつかの誤解があり、それがまるで物語が途中で止まってしまったように見えてしまっているのです。
けれど、実際には『ニセモノの錬金術師』は打ち切りになっていません。
むしろ今も物語は続いており、作者・杉浦次郎さんと作画担当のうめ丸さんによって、着実に世界が広がっています。
ここでは、その「打ち切り説」がどこから出てきたのか、そして今どのように作品が展開しているのかを、順を追って見ていきましょう。
SNSや掲示板で流れた「打ち切り説」の発端
噂のきっかけは、X(旧Twitter)や掲示板などで「更新が止まった」「第一部が完結した」という投稿が拡散されたことでした。
特にpixivで公開されていた「ラフ版」が完結を迎えたとき、多くの読者が「終わってしまったのか」と受け止めてしまったようです。
ラフ版の最終話「後編:たいせつなもの」では、主人公パラケルススの旅が一つの区切りを迎えます。
その内容があまりにも壮大で、結末のような印象を与えたことも誤解を強めました。
読者の中には「ここで終わるのはもったいない」「続きを描いてほしい」という感想が多く投稿され、そこから「打ち切りだったのでは」という憶測が生まれたのです。
さらに、商業版が単行本3巻までしか発売されていなかった時期には、「続刊が出ない=打ち切りでは?」という声もありました。
しかしこれは単なる制作スケジュールの都合であり、作品自体が中断したわけではありません。
ラフ版完結と商業版の進行が同時期に重なったことで、結果的に“作品が止まったように見えた”のです。
商業版はKADOKAWA「カドコミ」で連載継続中
現在、『ニセモノの錬金術師』の商業版はKADOKAWAの漫画配信サイト「カドコミ」で連載されています。
原作は杉浦次郎さん、作画はうめ丸さん。
pixiv時代のラフ版をベースに、構図やセリフ、設定をブラッシュアップした“完全版”のような形で再構築されています。
商業版の特徴は、ラフ版の勢いを保ちながらも、絵の美しさや演出が格段に進化している点です。
うめ丸さんの描くキャラクターは繊細で、感情の揺れが細やかに伝わります。
特に、序盤で奴隷の少女を買うシーンでは、ただの「異世界ハーレムもの」とは一線を画す静かな緊張感があり、主人公の善良さと迷いが丁寧に描かれています。
また、物語のテンポも商業版では調整されており、キャラクター同士の関係性や世界の仕組みがより分かりやすく整理されています。
ラフ版のときに「情報量が多すぎて難しい」と感じた読者も、商業版ではすんなり物語に入り込めるようになっているのです。
現在の連載状況を整理すると、次のようになります。
| 作品形態 | 状態 | 内容の特徴 |
|---|---|---|
| pixivラフ版 | 完結済(第一部) | 無料公開。全3編構成。荒削りながら熱量が高い。 |
| 商業版(カドコミ) | 連載継続中 | ラフ版を再構成。絵と構成がブラッシュアップ。 |
| 外伝作品『スカイファイア』など | 公開中 | 本編世界とリンクするスピンオフ。 |
このように、商業版の連載は今も続いており、打ち切りではなく「進化」の途中にあります。
特に4巻以降は、「願い」と「呪い」という作品テーマが深く掘り下げられる展開が待っていると予告されており、今後への期待が高まっています。
pixiv版(ラフ版)は第一部が完結済み
打ち切りと誤解されやすいもう一つの理由が、pixivに掲載されていた「ラフ版」の構造です。
このラフ版はもともと、杉浦次郎さんが個人で発表していたもので、「前編:鏡の世界」「中編:宇宙編」「後編:たいせつなもの」の3部構成になっています。
そして「第一部完結」と明記されたことで、多くの読者が“物語の終わり”と捉えたのです。
けれど、実際にはこれは「シリーズの一区切り」であり、世界そのものが終わったわけではありません。
物語の舞台となる「照応効果」のある世界――“同一とみなされるものが同期する”という独自の法則――は、後の展開でさらに大きな意味を持ちます。
つまり、第一部はその世界観を形づくる“プロローグの集大成”なのです。
ラフ版を読んだ人の多くが印象に残るのは、やはり後半で描かれる「願い」と「呪い」の対比でしょう。
誰かを救おうとした“願い”が、別の誰かにとっての“呪い”になる。
その悲しさと皮肉が静かに積み重なっていく。
このテーマの深さが、後に商業版でより明確に描かれていく伏線になっています。
ラフ版を最後まで読むと、確かに一つの物語として完結したような満足感があります。
ですが同時に、「この先の世界がどうなるのか」「別の人物の視点から見たらどう映るのか」という余白も残されています。
その余白こそが、商業版や外伝作品へとつながる“扉”になっているのです。
ラフ版をまだ読んでいない人にとっては、商業版を追いながら、無料で読めるラフ版を並行して読むのもおすすめです。
両方を知ることで、「同じシーンなのに意味が違って見える」瞬間に何度も出会えます。
たとえば、序盤で描かれる少女の微笑みが、ラフ版では希望に見え、商業版では覚悟に見える。
そんな細やかな違いが、作品の奥行きを増しているのです。
完結=打ち切りと誤解された理由
「ニセモノの錬金術師が打ち切りになった」という噂が出た大きな理由は、「完結」という言葉が持つ印象にあります。
pixivで公開されていたラフ版の最終話に「第一部完結」と明記されていたため、多くの読者が「物語そのものが終わった」と受け止めたのです。
ところが、ここでの「完結」は、物語の“区切り”を意味していました。
実際のところ、ラフ版の物語は「前編:鏡の世界」「中編:宇宙編」「後編:たいせつなもの」という三部構成で描かれており、それぞれが一つの長編を成しています。
その最後の章「たいせつなもの」は、主人公パラケルススが自分の“願い”と向き合うシーンで終わります。
この章のラストでは、登場人物たちの想いが交錯し、「終わった」という感覚よりも「新しい始まりの前触れ」のような余韻が残されていました。
しかし、pixiv上での掲載がそこで一旦止まったこと、またその後すぐに商業版が始まったことで、読者の中には「ラフ版が打ち切りになり、商業版に切り替わったのでは」と考える人もいました。
また、ラフ版の絵柄が荒削りながらも情熱的だったこともあり、「描くエネルギーが尽きてしまったのでは」と心配する声もありました。
実際には、ラフ版を描き上げたあとに杉浦次郎さんは、作画担当を迎えて“より完成された形”で商業版を再構築することを決めていたのです。
つまり、ラフ版の完結は「打ち切り」ではなく、「商業版へと進化するためのステップ」でした。
読者が感じた寂しさは、物語が止まったからではなく、一区切りがついたことで一瞬静けさが訪れたためでしょう。
この関係を整理すると、次のようになります。
| 状況 | 解釈の違い | 実際の意味 |
|---|---|---|
| pixiv版「第一部完結」と記載 | 物語が終わったと思われた | 物語の一章が終わり、新しい展開に向かう |
| 商業版への移行 | ラフ版が打ち切りになったように見えた | より完成された形での再構築・連載継続 |
| 一時的な更新停止 | 作品が止まったように見えた | 制作体制の変更・準備期間中 |
このように、言葉の受け取り方とタイミングの重なりが、「打ち切り説」を生んでしまったと言えるでしょう。
作者・杉浦次郎氏は現在も創作活動を継続
作者の杉浦次郎さんは、今も精力的に創作活動を続けています。
代表作『僕の妻は感情がない』では、心を持たない家電ロボットと人間の夫婦を描き、ハートフルで優しい作風が人気を集めました。
この作品が持つ“優しさの中にある痛み”という感覚は、『ニセモノの錬金術師』にも共通しています。
実際、杉浦さんのX(旧Twitter)では、たびたび『ニセモノの錬金術師』関連の投稿が行われています。
「異世界で奴隷の女の子を買ったら利益が出すぎてしまう話」という投稿では、物語の冒頭部分が紹介されました。
一見すると定番の異世界設定ですが、読み進めるうちに、それが“チートもの”ではなく“願いと呪いの物語”であることがわかってきます。
そのギャップと深さが、読者を強く引き込んでいるのです。
また、杉浦さんの創作は“設定の厚み”にも特徴があります。
たとえば『ニセモノの錬金術師』で登場する「照応効果」という概念。
「同一とみなされるものは同期する」というこの設定は、単なる魔法のルールではなく、人間関係や価値観にも影響を与える哲学的な仕掛けになっています。
こうした緻密な設定を生み出すために、杉浦さんは日々構想を練り、作品世界を拡張しているのです。
さらに、ラフ版以降の物語として『スカイファイア』や『神引きのモナーク』などの関連作品も展開しています。
特に『スカイファイア』は“第100部”として位置づけられており、『ニセモノの錬金術師』と深い世界的なつながりを持っています。
これらの作品が同時に進行していることからも、杉浦さんが“物語を終わらせる”のではなく“広げている”ことがわかります。
彼の創作スタンスは一貫しています。
「完璧ではないからこそ、人は願う」。
このテーマが根底にあり、作品ごとに異なる形で表現されているのです。
『ニセモノの錬金術師』もまた、そのテーマの延長線上にあります。
だからこそ、この物語が“終わる”というよりも、“続いていく”という感覚を強く持つのでしょう。
作画担当・うめ丸氏とのタッグも続行中
商業版の『ニセモノの錬金術師』では、作画を担当しているのがうめ丸さんです。
ラフ版では杉浦次郎さん自身が絵を描いていましたが、商業版では物語をより美しく、読みやすく伝えるためにプロの作画担当が参加しました。
うめ丸さんの絵は、キャラクターの感情表現がとても豊かです。
特に印象的なのは、序盤でパラケルススが奴隷の少女を買うシーン。
ラフ版では勢いのある筆致で描かれていましたが、商業版では光と影のコントラストが強調され、二人の間に生まれる小さな信頼の芽が丁寧に描かれています。
まるで絵の中に「沈黙の会話」があるようで、見るだけで心が揺れる瞬間があります。
また、戦闘シーンや錬金術の演出も迫力を増しました。
うめ丸さんのタッチは、細かい線と緻密な構図で“静かな緊張感”を作り出します。
ただ派手なだけでなく、キャラクターの心の動きが視線や手の動きから伝わるのです。
この繊細な描写が、作品全体の深みをさらに強めています。
うめ丸さんはSNSでも制作過程や新刊情報を発信しており、読者との距離が近いことも魅力です。
作画担当が積極的に情報を共有していることで、「まだ続いているんだ」「新刊を楽しみにしていていいんだ」と安心できるファンも多いでしょう。
二人のタッグは、単なる原作と作画の関係を超えています。
杉浦さんの世界観と、うめ丸さんの表現力がかけ合わさることで、『ニセモノの錬金術師』という唯一無二の作品が生まれています。
そして、このタッグは今も続いています。
商業版の物語はまだ序盤。
杉浦さんが描きたかった“願いと呪いの物語”の核心には、まだ誰もたどり着いていません。
だからこそ、今の『ニセモノの錬金術師』は「打ち切り」ではなく、「これから本当の核心へと向かう途中」なのです。
『ニセモノの錬金術師』打ち切りと誤解される背景と真相
「ニセモノの錬金術師」が“打ち切りになった”という声は、実際には誤解から生まれたものです。
その背景には、pixivで公開されていた「ラフ版」と、現在KADOKAWAの「カドコミ」で連載されている商業版との関係が深く関わっています。
両者はまったく別の作品ではなく、同じ物語を異なる形で描き直している関係にあります。
そのため、pixivの更新が止まったときに「終わってしまった」と感じた人が多かったのです。
この章では、ラフ版と商業版の関係や、「第一部完結」という言葉がなぜ誤解を生んだのかを整理しながら、作品の全体像を明らかにしていきます。
そして最後に、『スカイファイア』という“第100部”の存在から見える、壮大な世界のつながりにも触れます。
pixivラフ版と商業版の関係を整理
まず知っておきたいのは、pixivで公開されていた「ラフ版」と商業版は、同じ物語の異なる段階にあるということです。
ラフ版は杉浦次郎さんが個人で描き上げた、いわば“試作版”です。
線は荒い部分もありますが、ストーリーや設定の骨格はこの段階でほとんど完成していました。
そのラフ版をベースに、商業版では作画をうめ丸さんが担当し、演出や構成が練り直されています。
商業版の方は絵が格段に美しくなり、キャラクターの感情描写や背景の情報がよりわかりやすく整理されています。
それにより、ラフ版の勢いと深さを保ちながらも、より広い読者層に届く形になっているのです。
たとえば、ラフ版の序盤では「奴隷の少女を買う」シーンが物語の始まりとして描かれています。
ここでは、異世界ファンタジーにありがちな導入かと思いきや、主人公パラケルススの“他者を救うために行動する矛盾”が細やかに描かれています。
商業版ではこの場面の構図や表情が丁寧に再構成され、パラケルススの“優しさと危うさ”がより伝わるようになっています。
つまり、ラフ版は「アイデアと熱量の原石」であり、商業版はそれを磨き上げた「完成された形」なのです。
両者の関係を整理すると、次のようになります。
| 項目 | pixivラフ版 | 商業版(カドコミ連載) |
|---|---|---|
| 作者 | 杉浦次郎(原作・作画) | 原作:杉浦次郎/作画:うめ丸 |
| 状況 | 第一部完結済 | 連載継続中(単行本3巻まで) |
| 内容 | 物語の原型。無料で公開中 | ラフ版を再構成。絵・演出を刷新 |
| 特徴 | 熱量重視で荒削りな表現 | 美しいビジュアルと整理された構成 |
| 関係性 | 原作の原型 | 正式なリメイク・発展形 |
このように整理すると、「ラフ版の完結=物語の終わり」ではなく、「ラフ版の完成=商業版の始まり」であることがわかります。
pixivでの更新停止が“打ち切り”ではなく、“商業版への引き継ぎ”だったのです。
「第一部完結」はストーリー構造上の区切り
pixivラフ版の最終話には「第一部完結」と明記されています。
この言葉が「物語全体の終了」と誤解されてしまったのも、打ち切り説が広がった理由のひとつです。
しかし、実際には「第一部」という言葉の通り、それは長い物語の“一区切り”に過ぎません。
『ニセモノの錬金術師』の第一部は、「前編:鏡の世界」「中編:宇宙編」「後編:たいせつなもの」の3章構成です。
これらは一見別々の物語のように見えますが、全体を通して“願いと呪い”というテーマでつながっています。
たとえば、「鏡の世界」では、同一とみなされる物は同期するという“照応効果”の法則が登場します。
ここで描かれるのは、自己と他者の境界が曖昧になる恐ろしさであり、それが“願いの裏側にある呪い”の象徴となっています。
続く「宇宙編」ではスケールが一気に拡大し、個人の願いが宇宙規模の災厄へと繋がっていく。
そして「たいせつなもの」では、その災厄の中で人が何を選ぶのかが問われるのです。
ラフ版の最終ページでは、パラケルススが大切なものを手放す決断をします。
それは終わりではなく、「次の物語へ進むための犠牲」として描かれています。
静かな余韻の中に「また歩き出す」気配があり、このシーンが第一部の締めくくりとなりました。
つまり、「完結」という言葉は、物語の終了ではなく、主人公の一つの旅の終着点を意味していたのです。
ラフ版が第一部で止まっているのは構造的な理由であり、続きは商業版や外伝へと受け継がれています。
物語はまだ序章!“第100部”『スカイファイア』へ続く世界
そして『ニセモノの錬金術師』の世界は、第一部で終わりではありません。
実は、ラフ版の外伝として『スカイファイア』という作品が存在します。
この作品はなんと、“ニセモノの錬金術師 第100部”という位置づけで描かれています。
この数字に驚いた読者も多いでしょう。
「第100部」とは、物語の構造上、無数の“願いと呪いの連鎖”が世界中に存在することを示唆しています。
つまり、『ニセモノの錬金術師』というタイトルそのものが、ひとつの世界を軸にした壮大な群像劇の入口に過ぎなかったのです。
『スカイファイア』の物語では、錬金術という技術が“神の火”として扱われ、人間の欲望と破滅を象徴する存在になります。
読者がラフ版を読んだあとにこの作品を見ると、そこに登場する登場人物たちの行動原理が“ニセ錬”のテーマである「願いと呪い」と深く繋がっていることに気づきます。
この“第100部”という表現は、作者が構想している世界観の広さを示すメタファーでもあります。
つまり、第一部が完結したとしても、物語そのものはまだ始まったばかり。
今後も異なる視点や時代、世界を通して、このテーマは繰り返し描かれていくのです。
この構成を理解して読むと、「打ち切り」どころか、むしろ“壮大な設計図の一部”であることがわかります。
杉浦次郎さんは『ニセモノの錬金術師』という一本の物語を描いているのではなく、願いと呪いの系譜を描いているのです。
まとめると、次のようになります。
| 要素 | 内容 | 解釈 |
|---|---|---|
| 第一部完結 | パラケルススの旅が一区切り | 物語全体の序章にあたる |
| 商業版 | 第一部の再構築と拡張 | 世界観の整理と深化 |
| 『スカイファイア』 | 第100部として展開 | 世界観の拡張・群像劇化 |
こうして見れば、『ニセモノの錬金術師』は決して打ち切られた作品ではなく、むしろ今まさに広がり続けている物語です。
ラフ版が終わったあとも、その“火”は別の場所で燃え続けている。
そして、その火はこれからも新しい物語を生み出していくのです。
作品テーマ「願いと呪い」は今後さらに深まる
『ニセモノの錬金術師』という作品を語る上で欠かせないのが、「願い」と「呪い」というテーマです。
物語の根幹には、人が何かを強く願うとき、その願いが必ずしも幸福を生むわけではない、という現実があります。
この二つの感情は、作品を通して鏡のように描かれており、登場人物たちの選択や葛藤を深く掘り下げる装置として働いています。
主人公パラケルススは、錬金術師として「人を救いたい」という願いを持っています。
しかし、その行動が思いもよらぬ悲劇を呼び込む場面も少なくありません。
序盤の印象的なシーンに、奴隷の少女を買うくだりがあります。
そこでは、彼の“優しさ”が確かに存在するのに、その善意が世界の理に触れると、まるで呪いのように反転してしまう。
この構造が、『ニセモノの錬金術師』の根幹を成しているのです。
また、このテーマは単なる人間ドラマではなく、「照応効果」という世界設定によって裏付けられています。
“同一とみなされるものは同期する”というこの法則は、願いの持つ連鎖や影響を象徴しています。
誰かが誰かのためを思って行動することで、別の誰かの現実を歪めてしまう。
それが「呪い」として跳ね返ってくるのです。
商業版では、これまでに提示されたこのテーマがさらに深化していくと予想されています。
とくに4巻以降では、登場人物それぞれの願いが絡み合い、個人の想いが世界の在り方そのものを揺るがす展開が控えています。
ラフ版でもその片鱗は描かれていましたが、商業版では心理描写や対話がより丁寧に描かれることで、「願いと呪い」がより哲学的な問いとして浮かび上がっていくでしょう。
作品の中で、あるキャラクターが「どれを摘み、どれに水をやるかはあなたの魂が選びなさい」と語る場面があります。
これは、この物語全体を象徴するセリフのひとつです。
願いも呪いも、誰かが意図して作るものではなく、自分の選択が世界を変えていく。
そのテーマが、今後さらに深く掘り下げられていくことが期待されています。
商業版4巻以降から始まる“ゲームチェンジ展開”
『ニセモノの錬金術師』の商業版は、序盤から中盤にかけては比較的静かな展開が続きます。
登場人物や世界の法則を丁寧に説明しながら進むため、最初の数巻だけを読んだ人には「スローライフ系の異世界漫画」と感じられるかもしれません。
しかし、3巻の終盤から4巻にかけて、物語は大きく方向転換します。
この転換点は、ファンの間で「ゲームチェンジ」と呼ばれています。
それまでの世界観のルールやキャラクター同士の関係が一変し、「異世界で生きる話」から「人間の在り方を問う話」へと進化するのです。
具体的な展開を大きく語ることは避けますが、たとえば照応効果の応用によって、「同一」とは何かという根源的な問いが提示されます。
命・記憶・存在――それらを同一とみなすことの是非。
その瞬間、物語は単なるファンタジーではなく、哲学と倫理を含んだ人間劇へと変貌します。
この展開により、それまで描かれてきた“日常”が一度崩壊します。
それは物語の終わりではなく、本当の意味での始まり。
作者の杉浦次郎さんは、この構成を意図的に設計していたようで、序盤の穏やかさが、後半の衝撃をより際立たせるための“静かな前奏曲”になっています。
私も初めて読んだとき、3巻までと4巻以降ではまるで別の作品を読んでいるような感覚を受けました。
それほどまでに、物語の密度と緊張感が変わるのです。
この「ゲームチェンジ」が起こる瞬間に立ち会えることが、『ニセモノの錬金術師』を読む大きな魅力の一つだと感じます。
読者の誤解を招いた「更新間隔」と「展開の静けさ」
一方で、こうした構成の妙が、結果的に「打ち切り説」を呼ぶ原因にもなりました。
その理由のひとつが、「更新間隔」と「展開の静けさ」です。
『ニセモノの錬金術師』の商業版は、章ごとに緻密な構成を持つため、更新間隔が他の作品よりも長い時期がありました。
特に3巻から4巻にかけては、物語の転換を支える設定の整理や、作画の演出調整などが行われていた時期で、更新が一時的に止まっていたのです。
その結果、「更新が途絶えた=連載が止まった」と誤解されてしまった読者も少なくありません。
また、序盤の“静かな日常描写”も誤解を招きました。
主人公と少女のやり取りや、村での生活描写などが続くため、「このまま終わってしまうのでは?」と感じた人もいたのです。
しかし、それらは後に来る大きな展開の“下地”として描かれていたものでした。
ラフ版を読んだ人は知っている通り、物語の本番はむしろそこから始まります。
読者の期待とのギャップをまとめると、こうなります。
| 読者の印象 | 実際の意図 |
|---|---|
| 更新が止まった=打ち切り? | 制作期間の調整・再構成 |
| 日常シーンが多い=盛り上がりがない | 後半の転換を引き立てるための静けさ |
| 3巻で一区切り=完結? | むしろ4巻以降が本編の核心 |
つまり、作品のテンポや更新間隔の“静けさ”が、誤解を生み出しただけであり、内容自体はむしろ綿密に設計されていたのです。
むしろ“打ち切りではなく拡張中”な理由
結論として、『ニセモノの錬金術師』は打ち切りではなく、むしろ“拡張中”の作品です。
pixivラフ版が完結し、商業版で再構築され、さらに外伝の『スカイファイア』や『神引きのモナーク』へと物語の世界が広がっています。
この“拡張”は、単なるスピンオフ展開ではありません。
それぞれの作品が独立していながら、同じ「願いと呪い」のテーマを共有しており、まるで一つの巨大な宇宙のように連結しています。
たとえば、『スカイファイア』では錬金術という技術が“神の火”と呼ばれ、人間の進化と破滅の象徴として登場します。
その思想は、『ニセモノの錬金術師』で描かれた“人の手でホンモノを作ろうとする矛盾”をさらに拡大させたものです。
一方、『神引きのモナーク』では、現代的な視点で“選ばれることの呪い”が描かれています。
これらを読むと、杉浦次郎さんがどれだけ緻密にテーマをつなぎ合わせているかが見えてきます。
今後、商業版の4巻以降では、この“拡張”がさらに顕著になるでしょう。
ラフ版の後半に存在した哲学的な問い、「ニセモノとは何か」「ホンモノとは何か」が、より明確に語られるはずです。
そしてそれは、おそらく“第100部”に繋がる物語の土台でもあります。
『ニセモノの錬金術師』は、止まったのではなく、形を変えて広がり続けている。
この作品を「打ち切り」と呼ぶのは、まだ夜明け前の空を見て“日が沈んだ”と言うようなものです。
本当の光は、まだこれから現れるのです。
アニメ・映画が大好きで毎日色んな作品を見ています。その中で自分が良い!と思った作品を多くの人に見てもらいたいです。そのために、その作品のどこが面白いのか、レビューや考察などの記事を書いています。
詳しくはこちら


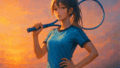

コメント