実写映画『進撃の巨人』(2015年)は公開当時から賛否両論を巻き起こしました。
特に批判の矛先となったのが、脚本を手掛けた映画評論家・町山智浩さんです。
「原作を無視した改変がひどい」との声が多い一方で、実はその裏には原作者・諫山創先生の意向や、業界の事情が深く絡んでいました。
この記事では、町山智浩さんの脚本がなぜ問題視されたのか、そしてその背景にある真相を掘り下げます。
実写版『進撃の巨人』の基本情報と公開当時の反応
2015年に公開された実写映画『進撃の巨人』は、当時の邦画の中でも最大級の注目を集めた作品でした。人気漫画の映像化であり、しかも原作はすでに世界中で大ヒットしていたため、公開前から期待と不安が入り混じった空気が漂っていました。
配給は東宝、監督は特撮やVFXに強い樋口真嗣監督、脚本には映画評論家として知られていた町山智浩さんが参加するなど、製作陣は話題性抜群。さらに主演には三浦春馬さん、ヒロイン役に水原希子さん、ほかにも石原さとみさんや長谷川博己さんといった人気俳優がずらりと並び、まさに「邦画の総力戦」ともいえる布陣でした。
ここではまず、公開当時の状況やファンからの反応を整理しながら、なぜ大きな期待がやがて酷評に変わっていったのかを見ていきます。
2015年、邦画最大級の話題作として登場
実写映画『進撃の巨人』が公開されたのは、2015年8月と9月。前後編の二部作として発表され、それぞれにサブタイトルがつけられました。前編は『進撃の巨人 ATTACK ON TITAN』、後編は『進撃の巨人 ATTACK ON TITAN エンド オブ ザ ワールド』です。
公開前から大規模な宣伝が展開され、テレビCMや予告映像には「超大型巨人」が街を襲うシーンが登場し、迫力ある映像が話題を呼びました。特に予告編で軍艦島の廃墟を背景に巨人が現れるカットはインパクト抜群で、ファンの期待は一気に高まりました。
当時の邦画界では、これほどの規模でVFXを駆使した作品は珍しく、IMAXや4DXといった上映方式も同時に発表され、「ついに邦画もここまで来たか」と注目を集めたのです。
前後編二部作に分けられた制作事情
実写版が二部作になったのは、単なる作品の都合だけではありません。製作の裏側には、予算確保という大きな事情がありました。
『進撃の巨人』の世界観を再現するには、巨大な壁、立体機動装置、そして巨人たちを描くための大規模なCGが欠かせません。しかし邦画の制作費はハリウッドに比べて限られており、そのまま一作にまとめてしまうと十分な予算が得られない可能性が高かったのです。
そこで、前後編の二部作にすることで「二本分の予算」を確保し、スポンサーから資金を集めやすくする戦略が取られました。その結果、約30億円規模という邦画としては異例の大規模予算が実現しました。
撮影は2014年に長崎県の端島、通称「軍艦島」で行われ、廃墟を生かしたロケーションが話題に。さらにCG技術とミニチュア撮影を組み合わせるなど、スタッフは当時できる限りの工夫を凝らしていました。
このように、制作陣の努力や挑戦は確かに大きなものがありましたが、完成した映画は公開直後からファンの間で大きな論争を巻き起こすことになります。
公開直後、ファンから酷評
映画が公開されると、SNSやレビューサイトでは批判の声が噴出しました。
特に目立ったのは、「原作との違いが大きすぎる」という意見です。人気漫画を実写化する際に改変はつきものですが、今回の『進撃の巨人』ではキャラクター設定やストーリー展開が大きく変更され、原作ファンを戸惑わせました。
また、映像面では一部の巨人描写やアクションシーンに高い評価があったものの、肝心のストーリー展開が雑だと感じる観客が多く、全体として「迫力はあるが中身が伴っていない」という評価が広がっていったのです。
ここからは、なぜ酷評につながったのか、その理由を具体的に掘り下げていきます。
酷評の理由1:キャラクター改変の大きさ
最も大きな批判は、キャラクターの改変でした。主人公エレンやミカサ、アルミンといった主要キャラは登場するものの、性格や役割が原作とはかなり異なっています。
特にファンの間で問題視されたのは、エレンとミカサの関係性。原作では「家族であり仲間」という絆が描かれているのに対し、映画では恋愛色が強調され、ミカサがエレンを突き放す展開もあり、原作ファンにとっては違和感が大きかったのです。
さらに、映画オリジナルキャラである「シキシマ」(長谷川博己)がエレンに代わるリーダー的存在として描かれたことも、ファンからは「誰だこの人?」と受け止められました。
酷評の理由2:ストーリー展開の不自然さ
映画では、原作の「ウォール・マリア陥落」や「巨人との戦い」といった大筋をなぞりつつも、細部は大きく改変されています。
例えば、巨人との戦闘シーンは迫力がありながらも、登場人物たちの行動に説得力が乏しく、「なぜそうなるの?」という展開が多かったのです。
立体機動装置を駆使したアクションも、本来の爽快感より「慌ただしく何をしているのか分かりづらい」と言われることがありました。結果として、映像の迫力に比べてストーリーの厚みが不足し、観客は置いてけぼりになってしまったのです。
酷評の理由3:脚本家・町山智浩への強い批判
もう一つの大きな理由は、脚本を担当した町山智浩さんへの批判でした。
映画評論家として鋭い批評を行ってきた町山さんが、今度は自分自身の脚本で失敗したと見なされ、「評論家なのに自分はできなかったのか」という厳しい声が集まったのです。
さらに、町山さん自身が「原作通りの脚本は原作者に却下された」と発言したことも物議を呼びました。つまり「改変は原作者の意向でもあった」という主張ですが、ファンからすると「それでも脚本が面白くなかったのは事実だ」と受け止められたのです。
結果的に、評論家としての過去の発言と脚本家としての結果が「ブーメラン」のように自分に返ってきてしまい、町山さんへの批判が映画全体の酷評につながりました。
まとめ:酷評の背景を整理
最後に、公開直後に寄せられた批判の理由を整理してみましょう。
| 酷評の理由 | 内容 | ファンの反応 |
|---|---|---|
| キャラクター改変 | エレンとミカサの関係性の変更、オリキャラ登場 | 「原作の魅力が消えた」 |
| ストーリー展開 | 不自然で説得力に欠ける流れ | 「映像はすごいが話が雑」 |
| 脚本家への批判 | 町山智浩へのブーメラン的批判 | 「評論家なのに失敗した」 |
こうして振り返ると、実写版『進撃の巨人』が酷評されたのは単なる「原作改変」だけではなく、物語の説得力不足や脚本家への過剰な期待も重なったことが分かります。
それでも、この映画が挑戦したスケール感や技術的な試みは邦画史の中で大きな意味を持ち、今も語り継がれる存在となっています。
町山智浩が脚本を担当した経緯
実写映画『進撃の巨人』の脚本を担当したのは、映画評論家として知られていた町山智浩さんでした。彼は普段、アメリカ映画を中心に深い考察を発信し、多くの映画ファンから信頼を得ていた人物です。そんな町山さんがなぜ突然、大人気漫画の実写化という大仕事の脚本を担うことになったのか――そこには映画業界ならではの事情と、原作者・諫山創先生との関係がありました。ここでは、その経緯をたどっていきましょう。
評論家から脚本家へ――異色の挑戦
町山智浩さんは、元々はアメリカ映画に精通した映画評論家として名を知られていました。彼の語り口は歯に衣着せぬ鋭さで、時には「この監督は原作を理解していない」と辛辣な批評をすることもありました。そんな人物が、まさか自分で脚本を書く立場に立つとは多くの人が想像していなかったでしょう。
しかし、実写版『進撃の巨人』の制作が動き出したとき、町山さんの名前は突然脚本家の欄に現れました。彼自身も「評論家だから本職ではない」と語っていますが、それでも起用されたのは、彼の映画に対する知識量や独自の視点に期待されたからでした。
ただし、この「評論家から脚本家へ」という異色の挑戦は、のちにファンから「評論していた側が自分でやって失敗した」と手厳しい批判を受けることにつながっていきます。
中島哲也監督降板後に町山脚本が採用された背景
当初、実写版『進撃の巨人』の監督は『告白』などで知られる中島哲也監督が務める予定でした。中島監督は斬新な映像表現で知られる人気監督ですが、企画段階で降板してしまいます。その理由は明らかにはされていませんが、制作サイドとの意見の違いがあったとされています。
監督が降板したことで企画は一度振り出しに戻り、脚本も大きく見直されることになりました。そこで新たに脚本に抜擢されたのが町山智浩さんです。評論家としての知識と、物語に対する分析力を買われたのでしょう。
監督が樋口真嗣さんに決まったタイミングで、町山さんが脚本に本格的に関わり始めます。評論家が一気に最前線のクリエイターへと移行するという珍しい人事は、映画業界でも驚きをもって受け止められました。
諫山創から「原作通りは却下された」という証言
町山さんはのちに、「原作通りの脚本を提出したが、諫山創先生自身から却下された」と語っています。諫山先生は「原作をそのまま実写化しても面白くない」と判断し、オリジナル要素を盛り込んだ展開を求めたというのです。
つまり、映画で大きく改変されたストーリーやキャラクターは、町山さんだけの独断ではなく、原作者の意向も含まれていたことになります。
ただし、この発言がファンの心を完全に納得させることはできませんでした。多くのファンにとっては「誰が言ったかは関係ない、出来上がった映画が面白くなかった」という思いが強かったからです。
改変はなぜ行われたのか?
では、なぜ原作から大きく改変されたのでしょうか。そこには町山さん自身の考え方や、諫山創先生の判断、そして邦画という枠組みでの限界がありました。ここからは、改変の理由や意味を掘り下げていきます。
町山智浩が語った「原作そのままではダメ」理論
町山さんはかつて評論家として、「実写映画は原作をそのまま再現するだけでは失敗する」と語っていました。彼の理論では、映画には映画の尺や表現方法があり、漫画のすべてを盛り込むことは不可能。だからこそ大胆な取捨選択や改変が必要だというのです。
その思想がそのまま『進撃の巨人』に持ち込まれました。実際、実写映画版は舞台設定やキャラクターの関係性を大きく変え、特に主人公エレンとヒロインのミカサの関係を恋愛色強めに描きました。これは、限られた上映時間の中で観客に分かりやすいドラマを作るための工夫でもあったのです。
ただ、その工夫が裏目に出てしまい、原作ファンからは「原作の魅力を壊してしまった」と受け取られました。
諫山創が町山を信頼していた証拠――ハンジのモデルに?
実は原作者の諫山創先生は、町山智浩さんをかなり信頼していたことが分かっています。その証拠のひとつが、人気キャラクター「ハンジ・ゾエ」のモデルが町山さんだと言われていることです。
ハンジといえば、巨人の研究に夢中になりすぎて暴走するシーンが印象的な人物。好奇心旺盛で突拍子もない行動をとるその姿は、どこか評論家としての町山さんの姿と重なります。諫山先生がそんな人物を物語の中心人物に据えたということは、町山さんへのリスペクトがあったことの表れでしょう。
だからこそ、諫山先生が「原作通りではなくオリジナル要素を入れてほしい」と町山さんに託したのは自然な流れだったのかもしれません。
改変そのものは悪ではなかったという視点
改めて考えると、改変そのものが必ずしも悪いわけではありません。実写映画というフォーマットに合わせるためには、原作の長大な物語をそのまま描くことは不可能です。
むしろ、改変を通して新しい解釈を提示したり、実写ならではの魅力を引き出すことが成功する道だったともいえます。実際に、巨人の造形や軍艦島でのロケなど、実写だからこそ迫力を出せた部分もありました。
問題は、その改変が観客にとって納得できるものだったかどうかです。エレンとミカサの関係や、オリジナルキャラクター・シキシマの存在は、結果的に観客を戸惑わせる要素となってしまいました。
ファンが納得しなかった脚本の穴
実写版『進撃の巨人』が公開されたとき、特に多くの批判が集まったのは脚本の部分でした。映像や巨人の造形は迫力があり、技術的には邦画として挑戦的な作品でしたが、物語の流れやキャラクターの描かれ方が大きな違和感を残したのです。
原作の魅力を知っているファンにとっては、「なぜあのキャラがこんな風に描かれているのか」「なぜそんな展開になるのか」と首をかしげるシーンが連続しました。ここでは、脚本における具体的な“穴”とされる部分を見ていきましょう。
キャラクター設定の改変が大きすぎた問題
まず最も指摘が多かったのは、キャラクターの設定が原作から大きく変わっていたことです。
主人公エレンは、原作では「自由を求める強い意志を持った少年」として描かれています。壁の外の世界に憧れ、巨人への激しい怒りを胸に戦いに身を投じる姿が多くの読者を惹きつけました。
ところが映画版では、その「熱さ」が薄まり、キャラクター性が曖昧になってしまいます。特に序盤で壁の外に出たい理由がぼやけて描かれ、「ただなんとなく流されているように見える」と感じた観客が少なくありませんでした。
さらにミカサも大きく改変されています。原作では常にエレンを守ろうとする強い仲間意識が特徴ですが、映画ではエレンを突き放すシーンがあり、彼女の冷淡さが強調されました。これにより「ミカサが原作と別人のようだ」という声が続出したのです。
オリジナルキャラ「シキシマ」への不満
そしてもう一つの大きな論争は、映画オリジナルキャラクター「シキシマ」の存在です。長谷川博己さんが演じたこのキャラは、立体機動装置を巧みに操り、エレンの前に立ちはだかるカリスマ的な兵士として描かれました。
しかし、原作には存在しない人物が映画の中心に据えられたことで、ファンの反応は複雑でした。物語上の重要な役割を担っていたにもかかわらず、その正体や背景は曖昧なままで、観客を納得させるまでには至りませんでした。
とくに後編では、シキシマが巨人化の秘密に関わる重要キャラクターとして登場する展開がありましたが、多くのファンから「無理やり感がある」「このキャラを出すくらいなら原作のリヴァイを出してほしかった」という声が上がりました。
「リヴァイの代わり」として作られたとも言われるシキシマですが、原作ファンにとっては消化不良な存在だったのです。
ストーリー展開の破綻と「説得力の欠如」
脚本の問題はキャラクター改変だけにとどまりません。物語の流れそのものにも、多くの「説得力の欠如」がありました。
例えば、巨人に襲撃されて壁が破壊されるシーン。原作では緊張感のある流れで人々が絶望に陥るのに対し、映画では展開が唐突で「なぜそうなるのか」が描かれないまま次々とシーンが進んでいきます。観客はキャラクターの感情についていけず、物語に没入できませんでした。
また、後半でエレンが巨人化するシーンも批判の的でした。原作では劇的なターニングポイントであり、彼の内面と葛藤がしっかり描かれるのですが、映画では突然の展開として扱われ、「説明不足」「ご都合主義すぎる」と受け止められたのです。
結果的に、映像の迫力と裏腹に、物語の流れに説得力がなく、観客が共感できる余地を失ってしまいました。
町山智浩への批判と“特大ブーメラン”
こうした脚本の問題は、やがて脚本を担当した町山智浩さん個人への批判につながっていきました。
映画そのものの出来に対する不満だけでなく、町山さんがこれまで「映画評論家」として数多くの作品を批評してきたことが、逆に自分への“特大ブーメラン”となってしまったのです。
評論家として他作品を批判してきた過去との矛盾
町山さんはこれまで、さまざまな映画を対象に「原作理解が浅い」「この展開は説得力がない」と辛辣な批評を行ってきました。その鋭さはファンから支持されてきた一方で、映画関係者からは恐れられる存在でもありました。
ところが自分が脚本を担当した『進撃の巨人』では、まさに町山さんが普段指摘していた「説得力の欠如」が噴出してしまったのです。
ファンからは「自分が言っていたことをそのまま突き返されている」と皮肉を込めて語られ、評論家としての姿勢と脚本家としての結果が真っ向から矛盾する形になりました。
盟友・宇多丸からも厳しい指摘
さらに町山さんにとって痛かったのは、ラジオ番組で長年コンビを組んでいた宇多丸さんからも批判が出たことです。
宇多丸さんは、町山さんをリスペクトしながらも、「作り手として批判を受けるのは当然」「評論家だからと言い訳はできない」と厳しく指摘しました。
この発言は多くのリスナーに「仲間内からもそう言われるなら仕方ない」と受け止められ、町山さんの立場をさらに苦しくしてしまいました。
「評論家だから本職じゃない」発言が火に油を注いだ
町山さん自身も映画公開後の批判に応える中で、「自分は評論家だから本職の脚本家ではない」という趣旨の発言をしました。
しかし、この言葉は逆効果でした。観客からすると「お金を払って見ているのだから、評論家だろうと関係ない」「プロとして参加した以上は責任を持つべきだ」と映ったのです。
結果的に、この発言が“言い訳”と受け止められ、さらに批判の炎を大きくすることになってしまいました。
業界的に見ると成功だった?
ファンからの酷評が目立った実写版『進撃の巨人』ですが、業界的な目で見ると「大失敗」とは言い切れません。むしろ、興行的にも制作手法的にも一定の成果を残したと評価される部分があります。批判が集中したのは脚本やキャラクター設定の問題でしたが、それとは別に「邦画としての挑戦」としては価値があったのです。ここでは、その裏側を整理してみましょう。
二部作にしたことで得られた予算確保の妙
実写映画『進撃の巨人』は、前後編の二部作として公開されました。この形式をとった背景には、制作費の確保という事情がありました。
邦画はハリウッド映画に比べると予算が圧倒的に少ないのが現実です。大規模なCGや特撮を駆使する『進撃の巨人』のような作品を、日本の映画業界で作るのは本来とても難しいことでした。
そこで製作陣は「二部作にすることで二本分の予算を確保する」という手法を取りました。スポンサーからも「二本の映画になるなら、その分投資効果がある」と理解を得られ、結果的に大規模なVFXや軍艦島での撮影など、邦画としては異例のスケール感が実現したのです。
映画そのものに批判はあっても、この予算戦略は業界的には巧みであり、後続の邦画作品にも影響を与える試みでした。
興行収入は邦画としては成功の部類
酷評を浴びた『進撃の巨人』ですが、興行収入の数字を見れば「失敗作」とは言えません。
前編は約32.5億円、後編も16.8億円を記録し、合わせて49億円近い成績を残しています。邦画市場では20億円を超えればヒット、30億円を超えれば大ヒットとされることが多いため、前編だけでも「成功」と呼べる水準でした。
もちろん、原作の人気や期待値を考えれば「もっと伸びてもおかしくなかった」という意見もあります。しかし、ファンの酷評が広がる中でも一定の観客動員を実現したことは、ブランド力と宣伝戦略の成果だったといえるでしょう。
表にまとめると、次のようになります。
| 指標 | 前編 | 後編 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 公開年 | 2015年8月 | 2015年9月 | – |
| 興行収入 | 32.5億円 | 16.8億円 | 約49.3億円 |
| 評価 | 酷評が目立つが動員は多い | 前編より減少 | 邦画としてはヒット |
結果だけを見れば「批判は多いが興行的には成功」という、非常に珍しい立ち位置の作品となりました。
VFX技術の挑戦と『シン・ゴジラ』への継承
もう一つ見逃せないのは、VFX技術への挑戦です。『進撃の巨人』では、実物大のセットに加え、ミニチュアをスキャンしてCGに取り込むという手法が取り入れられました。超大型巨人は造形物とCGを組み合わせることで迫力を演出し、軍艦島ロケと合成することで独特の荒廃感を生み出しています。
この試みは、後に同じ樋口真嗣監督が手がけた『シン・ゴジラ』(2016年)に継承されました。『シン・ゴジラ』は国内外で高く評価され、特撮映画の新たな地平を切り開いた作品となりましたが、その技術基盤の一部は『進撃の巨人』での挑戦があったからこそです。
つまり、『進撃の巨人』は「失敗作」と言われがちですが、技術面では邦画の進化に貢献した重要な一歩でもあったのです。
脚本批判は町山智浩だけの責任か?
映画公開後、批判の矛先は主に脚本を担当した町山智浩さんに集中しました。しかし、冷静に考えると「町山さん一人の責任」とするのは不公平でもあります。そこには、業界特有の力学や制作の事情が複雑に絡み合っていました。
講談社編集部の政治的な動き
『進撃の巨人』の映画化に大きく関わっていたのは、原作の出版社である講談社です。特に編集担当だった川窪氏は映画化プロジェクトの中でも強い発言力を持っていたとされます。
予算を集めるためのスポンサー交渉や、映画を二部作にする決定なども、講談社サイドの政治的な判断が影響していました。つまり脚本の改変は、必ずしも町山さんだけの意向ではなく、業界全体の事情が反映された結果でもあったのです。
諫山創の「すべて自分の責任です」という潔さ
さらに、原作者の諫山創先生自身が映画公開後に「すべて自分の責任です」と語っています。これは町山さんや監督をかばう意味合いもあったでしょうが、それだけでなく「原作通りではなく、オリジナル要素を入れる」という判断を下したのが自分であるという自覚があったからです。
諫山先生は町山さんを信頼し、映画版に独自性を持たせるよう依頼していたと言われています。だからこそ、最終的な出来に関しても潔く責任を引き受けたのです。この態度は多くのファンに感銘を与えましたが、同時に町山さんへの批判が余計に際立つ結果となりました。
町山一人に矛先が集中した構造的問題
結局のところ、映画の失敗部分を「誰の責任か」と探す流れの中で、最も目立って批判を浴びたのが町山智浩さんでした。評論家としての過去の発言がブーメランとなり、ファンやメディアの矛先が集中したのです。
しかし実際には、脚本だけでなく、制作全体の判断、編集部の動き、そして原作者の決断も絡んでいました。
このように考えると、実写版『進撃の巨人』の評価は「町山さんの脚本がすべて悪い」ではなく、「業界全体での挑戦の結果が期待に届かなかった」と見るべきでしょう。
今振り返ると見えてくる“実写進撃”の意義
公開から時間が経った今、あらためて実写版『進撃の巨人』を振り返ると、当時の批判だけでは語り尽くせない意義が見えてきます。確かに脚本やキャラクター描写には多くの不満が寄せられましたが、それでも「邦画でここまで挑戦した」という事実は残っています。ここでは、失敗と同時に得られた教訓や価値について整理してみましょう。
邦画で超大作を成立させる難しさ
『進撃の巨人』を実写化するという試みは、そもそも邦画にとって極めて大きな挑戦でした。
ハリウッドの大作映画では数百億円規模の予算がかけられるのに対し、邦画の制作費はその数分の一が限界です。巨人が人を食らう迫力ある映像、壁の崩壊、立体機動装置による空中戦など、原作の魅力を再現するには膨大なコストと技術が求められました。
制作チームは軍艦島ロケやCG合成、実物大セットの建造など、邦画の限界を押し広げる手法を取り入れました。そのスケール感は、それまでの邦画では考えられなかったレベルのものでした。
結果として「完全再現」には至らなかったものの、日本の映画業界が挑戦した「超大作邦画」の象徴的な一例となったのです。
誰が脚本をやっても成功は難しかった?
よく言われるのが「誰が脚本を担当しても難しかったのではないか」という見方です。
『進撃の巨人』の物語は、世界観の設定が非常に複雑です。壁の仕組み、巨人の正体、人類の歴史的背景など、多くの謎を積み重ねながら物語が展開していきます。これを2本の映画(合わせても3時間ほど)に収めるのは、構造的に無理がありました。
そのため、どの脚本家であっても「改変」は避けられなかったでしょう。もし原作を忠実に再現すれば説明ばかりの映画になり、観客は退屈してしまいます。逆に大胆に改変すれば、ファンから「原作を壊した」と叩かれる。この板挟みの中で脚本を作るのは、誰にとっても地獄のような仕事だったはずです。
町山智浩さんが批判を一身に受けましたが、そもそも「成功の難易度」が極端に高い企画だったのです。
町山智浩への同情論と再評価の動き
近年では、「町山さんを責めすぎではなかったか」という同情論も出てきています。
評論家として数々の映画を語ってきた町山さんにとって、この作品は初めての大規模な脚本挑戦でした。しかも原作者から「原作通りはダメだ」と求められるというハードルの高さ。さらに製作委員会やスポンサーの思惑も絡み、彼だけで自由に作れる状況ではなかったこともわかっています。
また、『進撃の巨人』で培われた映像技術や制作体制が『シン・ゴジラ』につながったことを考えると、「町山さんの脚本は荒削りだったが、挑戦自体は邦画の進化に寄与した」と再評価する声もあります。
当時の酷評は事実ですが、今となっては「邦画が世界に挑戦した一歩を支えた脚本家」として見直される動きも出てきているのです。
まとめ──『進撃の巨人』実写の教訓と町山智浩の立場
こうして振り返ると、実写版『進撃の巨人』は単なる「失敗作」ではなく、邦画が抱える課題と可能性を映し出した鏡のような存在でした。町山智浩さんの脚本は批判されましたが、その背景には必然も多く、挑戦の価値も確かにあったのです。
改変は必要悪だったが、完成度が伴わなかった
映画における改変は、もはや避けられないものでした。上映時間や予算、映像表現の制約を考えれば、「原作通り」はそもそも不可能です。
ただし、実写版ではその改変が観客に十分な説得力を持たず、結果的に「失敗」と受け止められてしまいました。必要悪としての改変は理解できても、完成度が足りなかったことが最大の問題だったのです。
脚本批判は受け入れるべきだが、挑戦の価値はあった
町山智浩さんが受けた批判は、作り手として避けられないものでした。評論家として他人の作品を厳しく論じてきた以上、自身の脚本も批評にさらされるのは当然です。
しかし同時に、挑戦したこと自体は大きな意味を持ちました。邦画で『進撃の巨人』を実写化するという困難な企画に取り組み、その過程で培われた技術やノウハウは確実に次の作品へとつながったのです。
読者・観客がどう感じるかこそが最終的な答え
結局のところ、映画の評価を決めるのは観客です。ある人にとっては「最悪の改変」であっても、別の人にとっては「邦画としては迫力があった」と感じられる。評価は一つに定まるものではありません。
町山智浩さんの脚本も、その評価は時代とともに変わっていくでしょう。批判の声が強かった公開当時から数年が経ち、「挑戦の意味」を評価する人が増えているのも事実です。
『進撃の巨人』実写版は、成功と失敗の両方を抱え込んだ特殊な作品でした。そしてその教訓は、「原作をどう実写化するのか」という問いを今も私たちに投げかけ続けています。
アニメ・映画が大好きで毎日色んな作品を見ています。その中で自分が良い!と思った作品を多くの人に見てもらいたいです。そのために、その作品のどこが面白いのか、レビューや考察などの記事を書いています。
詳しくはこちら


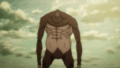
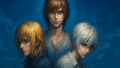
コメント