アニメで育った世代が初期の絵本版を開くと、「え、ちょっと怖い…」とたじろぐ瞬間があります。
薄暗い色調、ボロボロのマント、そして“自分の顔を差し出す”衝撃の場面。
けれど読み進めるほど、怖さの奥にあるやさしさや覚悟がにじみ出てくる――それが初期アンパンマンの魅力です。
本稿では、なぜ怖く感じるのかを整理しつつ、納得感のある“読み替え”の視点を提案します。
【アンパンマン】初期が怖いと感じる理由
初期のアンパンマンの絵本を手に取ると、まず感じるのは「アニメとは全然違う空気感」ではないでしょうか。
明るくて元気なアニメのイメージとは反対に、静かで薄暗く、どこか寂しさの漂う世界が広がっています。
この違和感こそ、多くの人が「初期アンパンマンって怖い」と感じた理由につながっています。ここでは、なぜそのように感じてしまうのかを、具体的な絵本の描写をもとに解きほぐしていきます。
絵本版の陰影とボロボロのマントが生む不安
初期の絵本「あんぱんまん」の1ページ目を開くと、夕暮れのような薄暗い空が広がっています。太陽は沈みかけ、空の色は赤と灰色が混ざり合っていて、明るさよりも影のほうが目に残ります。その中を、ボロボロのマントを羽織ったあんぱんまんがひとりで飛んでいる。この姿に、読者は自然と静かな不安を覚えます。
アニメのアンパンマンは、常に太陽の下で元気よく「アンパンマーン!」と飛び立ちます。しかし、絵本版のあんぱんまんは違います。声をあげることもなく、ただ空腹で倒れそうな旅人のもとに静かに降り立つのです。その表情も笑顔というより、どこか哀しみや覚悟を含んだような顔つきです。
さらに印象的なのは、そのマントです。破れて穴があき、端の糸はほつれている。今にも千切れそうなその布には、戦いの跡や旅の厳しさが刻まれています。やなせたかしさんは後に「正義を行う人はお金持ちじゃない。だから新しいマントを買えない」と語っています。このリアルで切ない設定が、読者の心を揺さぶります。
また、背景の描き方も不安を増幅させる要素です。ほとんどの場面で空は曇っており、風景に暖かな色はあまり使われていません。まるで世界そのものが飢えているかのように、寂れた村や荒れた大地が描かれています。そんな中で、自分の体を削って誰かを助けようとするあんぱんまんの姿は、優しさであると同時に、どこか切なく、そして少し怖く感じられるのです。
初期絵本とアニメの雰囲気の違い(比較表)
| 要素 | 初期の絵本 | アニメ版 |
|---|---|---|
| 空の色 | 夕暮れ・曇天が多い | 明るい青空 |
| アンパンマンの表情 | 物静かで真剣 | にこやかで明るい |
| マント | ボロボロに破れている | いつも新品のように綺麗 |
| 空飛ぶシーン | 音もなく静かに飛ぶ | 勢いよく飛び出す演出 |
| 世界の雰囲気 | 寂しさや貧しさが漂う | 温かく賑やか |
こうして見比べると、初期の絵本が「怖い」と言われるのは、視覚的な暗さだけでなく、「孤独」「貧しさ」「覚悟」といった感情が滲んでいるからだとわかります。
“顔を食べさせる”描写へのショック
初期のアンパンマンを語る上で避けて通れないのが、「顔を食べさせる」場面です。アニメでは、アンパンマンは手で自分の頬をちぎって差し出します。しかし絵本では、それよりも生々しい描写がされています。
空腹で倒れている旅人の前にあんぱんまんが降り立ち、ひざまずいてこう言います。
「ぼくのかおを たべなさい。」
旅人が驚いて断ると、あんぱんまんはさらに顔を近づけ、頭から直接かじるよう促します。旅人は涙を流しながら、その顔をかじる。あんぱんまんの顔はどんどん削れていき、ついには輪郭すらなくなってしまいます。
頭がなくなったあんぱんまんはどうなるのか――。なんとそのまま空を飛び立ち、ジャムおじさんのもとへ帰っていくのです。顔がないまま飛ぶ姿は、当時の子どもたちにも大人たちにも衝撃的でした。
この描写には「自分を犠牲にしても人を助ける」という強烈なメッセージが込められています。しかし同時に、体の一部を差し出すという行動は、生々しい“痛み”を想像させるため、怖さを感じる人も多かったのです。
やなせたかしさん自身は、この行為をこう語っています。
「正義はかっこよくなんかない。必ず傷つくものなんです。」
つまり、この“顔を食べさせる”シーンは単なるショック演出ではなく、「本当の優しさには痛みが伴う」という哲学そのものなのです。
8頭身→3頭身へ――初期造形の“人間っぽさ”
初期の絵本『あんぱんまん』を開くと、まず目につくのはその体型です。今ではおなじみの、丸くて小さく、3頭身のかわいらしいアンパンマンとはまったく違います。絵本の初期では、肩幅があり、手足も長く、まるで大人の人間のような8頭身の姿で描かれているのです。頭だけがあんぱんで、体はほぼ人間。胸には小さな“アンパンマーク”が描かれているくらいで、全体的にはヒーローというより旅人や兵士のような雰囲気を感じます。
この姿は子どもたちにとって、親しみやすいというより“知らない大人の顔をしたパンの人”という印象を与えやすかったのではないでしょうか。さらに、笑顔ではなく、どこか寂しげで達観したような表情をしていることもあり、温かさより静かな違和感を感じる読者も多かったはずです。
やなせたかしさんは後に、子どもたちの反応や編集部の意見を取り入れ、アンパンマンの頭身を大きく変えます。その結果、3頭身の丸い体、太い手足、大きな目のデザインへと進化していきました。幼児がぬいぐるみや人形として抱きしめられるサイズ感を目指したとも言われています。こうして初期の“人間っぽさ”はやわらぎ、今のような親しみやすいヒーロー像が生まれたのです。
変化を簡単に整理すると、以下のようになります。
| 項目 | 初期絵本(1973年頃) | 現在のデザイン |
|---|---|---|
| 頭身 | 7〜8頭身 | 2〜3頭身 |
| 表情 | 静かで感情を抑えた顔 | いつも笑顔で明るい |
| やせ型/丸み | やせた人間体型 | 丸みのあるぬいぐるみ体型 |
| 印象 | “ヒーローというより兵士” | “やさしく抱きしめられるヒーロー” |
この変化が、怖さをやわらげ、キャラクターとしての普及にもつながったと考えられます。
顔が無くても飛ぶ――“常識破り”の設定
もう一つ、多くの人に「怖い」と感じさせたのは、顔を食べられたアンパンマンの姿です。初期絵本では、お腹をすかせた旅人に顔をすべて食べられ、頭の形がなくなってしまう場面があります。それでもアンパンマンは倒れることなく、顔のないまま空を飛び、ジャムおじさんのもとへ帰っていくのです。
「顔がないのにしゃべる」「顔がなくても飛べる」という描写は、今のアニメには見られません。アニメ版では顔が濡れたり汚れたりすると力を失う、というルールが設定されていますが、初期ではそのルールがまだ存在しませんでした。頭部は単なる食料ではなく“命そのもの”として描かれています。だからこそ、自分の命を差し出す描写として、より強烈で衝撃的なのです。
このシーンは、子どもにとっては理解しにくい「死」「欠損」「自己犠牲」といったテーマと向き合う入り口にもなります。一方で、大人にとっては、命の象徴である顔を引き渡すアンパンマンの姿に、倫理的な葛藤や戸惑いを覚える人も多かったと言われています。
大人は酷評・幼児は熱狂――評価のギャップ
アンパンマンが初めて出版された当時、大人たちからの反応は厳しいものでした。「子どもに見せるものではない」「顔を食べさせるなんて残酷」「正義のヒーローが貧しいなんて夢がない」といった批判が寄せられたと、やなせたかしさん自身が語っています。
しかし、そんな中で一番最初にアンパンマンを受け入れたのは子どもたちでした。幼稚園や保育園では絵本の貸し出し回数が急に増え、「あのパンの顔のヒーローを読んで」とせがむ子も増えたと言います。大人たちが“残酷”と感じた顔を差し出す場面も、子どもたちは“助けてくれるやさしさ”として素直に受け止めていたのです。
なぜこのような評価の差が生まれたのでしょうか。それは読み手の視点の違いにあります。
| 読み手 | 感じ方 | 理由 |
|---|---|---|
| 大人 | 怖い・残酷・不安 | 顔=命や自己、欠損への恐怖や倫理観で捉えるから |
| 子ども | すごい・優しい・助けてくれる | 「自分のために分けてくれる」行為として受け止めるから |
やなせたかしさんはこう語っています。「純粋な子どもは、先入観も欲もない。だから本当に必要なものを感じ取る」と。つまり、初期アンパンマンにある“怖さ”は、子どもたちにとっては“本気の優しさ”として映っていたのです。
【アンパンマン】初期が怖いを“納得”に変える視点
初期のアンパンマンを読むと、怖さや違和感を覚える人が多いのは確かです。ですがその背景には、やなせたかしさん自身の人生経験や、本気で“正義とは何か”を考えた末にたどり着いた答えがあります。理由を知ることで、怖さはただの恐怖ではなく、深い意味や優しさとして心に残るものに変わります。ここではその視点をやさしく掘り下げていきます。
作者の戦争体験と「逆転しない正義」
やなせたかしさんは、若いころ戦争に兵士として参加しました。戦争の中では、昨日まで“正義”と言われていたことが、敗戦した途端に“悪”になることがあります。国が変われば敵と味方も入れ替わります。そうした経験から、やなせさんは「正義なんて簡単にねじ曲がるものだ」と感じたそうです。
でも、ひとつだけ変わらない正義があるのではないかと考えました。それが「飢えた人を助けること」「食べられない人に食べ物をわけること」です。これは国や立場が変わっても間違いではない。だからやなせさんの作るヒーローは、敵を倒すのではなく、まず人を助け、食べさせる存在になりました。
この想いは、絵本「アンパンマン」の冒頭から強く表れています。空腹で倒れ込む旅人の前に降り立ったアンパンマンは、ためらわず自分の顔を差し出します。血は出ません。悲鳴もありません。けれど、読者の胸に刺さる静かな痛みがあります。それは命そのものを削って誰かを助ける行為だからです。
大人が読めば「怖い」と感じるかもしれません。でもその怖さの裏には、やなせさんの「本物の優しさには痛みがある」という哲学があります。この“倫理の真剣さ”こそが、初期アンパンマンの怖さの正体だと言えるでしょう。
やなせたかしの正義の変遷
| 戦争体験前 | 戦争体験後 |
|---|---|
| 正義=敵を倒すこと | 正義=飢えた人を助けること |
| 強さ・武器がヒーローの条件 | 優しさ・献身がヒーローの条件 |
| 勝てば正しい | 食べさせれば正しい(逆転しない) |
アンパンマンの行動は、この「逆転しない正義」によって支えられています。だからこそ、顔をあげる姿は怖くもあり、美しくもあるのです。
マントが新調できない貧しさというリアリティ
もうひとつ、初期アンパンマンの怖さや切なさに関わっているのが、あのボロボロのマントです。絵本を注意深く見ると、マントの端は破れ、糸がほどけています。最初これを見た人の多くは「戦いで傷ついたのかな」と思いますが、実はもっとシンプルで現実的な理由があります。
やなせさんはこう語っています。「正義の味方って、お金持ちじゃないと思ったんです。だから新しいマントを買うお金がないんですよ」
アンパンマンは立派な城に住んでいるわけではなく、パン工場から空へ飛び立ち、戻ってきたらまたパンを焼きます。敵を倒すよりも、人を助けることに力を使います。だから名誉もお金も手に入らない。マントを買い直す余裕もありません。その“生活感”が、アンパンマンをただのヒーローではなく“血の通った存在”にしているのです。
マントが象徴する3つの意味
| マントの状態 | 象徴するもの |
|---|---|
| ボロボロに擦り切れている | 助け続けた時間と労力 |
| 新しくならない | 貧しさ・現実の厳しさ |
| 捨てずに使い続ける | 正義の継続、諦めない心 |
貧しさは悲しいことではなく、「正義とは格好つけることじゃない」「人を助けるためなら、自分の身なりなんて後回しでいい」という姿勢の表れです。だから、ボロボロのマントは、アンパンマンの誇りでもあります。
そして、この姿は子どもたちにとってリアルです。完璧すぎるヒーローよりも、少し傷つきながらも立ち上がる姿のほうが、心に残るのかもしれません。
「まず、食べさせる」――自己犠牲のヒーロー像
アンパンマンの行動を語るうえで欠かせないのは、「戦う前に、まず食べさせる」という姿勢です。一般的なヒーローは敵を倒し、世界を救います。しかしアンパンマンは、敵と戦うよりも先に、目の前で倒れそうな人や泣いている子どもを助けます。そのやり方は武器でも必殺技でもなく、自分の顔であるパンを差し出すことです。
初期の絵本では、このシーンが特に強烈です。旅人が寒さと空腹で倒れていると、アンパンマンは静かにひざまずき、「ぼくのかおをたべてください」と語りかけます。顔が食べられるたびに形が崩れ、ついには頭の上半分がなくなる場面も描かれます。それでも彼は苦しむことなく立ち上がり、自らの使命を果たしたように空へ飛び立ちます。
なぜここまでして食べ物を与えるのか。それは、アンパンマンの正義が「命を奪うこと」ではなく「命をつなぐこと」に根ざしているからです。やなせたかしさんは「正義の味方なら、まず飢えた人を助けなさい」と語りました。その正義には痛みが伴い、格好よさや派手さよりも、静かで深い覚悟が必要です。
アンパンマンの姿勢は、人間社会の「食べる側」と「食べられる側」という関係をあえて逆転させています。普通なら食べ物は命を支えるものですが、アンパンマンは“食べられる側”になることで、人の命を守る存在になります。この常識を越えた行為が、怖さであり、同時に美しさでもあるのです。
表にまとめると、アンパンマンのヒーロー像は次のように整理できます。
| ヒーローの種類 | 戦い方 | 目的 | 犠牲になるもの |
|---|---|---|---|
| 一般的なヒーロー | 敵を倒す | 平和を守る | 敵や物的被害 |
| アンパンマン | 食べさせる | 飢えを救う | 自分の顔・体そのもの |
この違いが、アンパンマンを唯一無二の存在として輝かせているのです。
私の読後感――怖さの奥ににじむ“やさしさ”
初めて初期の『あんぱんまん』を読んだとき、正直に言えば「ちょっと怖い」と思いました。暗い空、ボロボロのマント、血の代わりにあんこがこぼれる顔。それはアニメで見た明るく元気なヒーロー像とはまったく違っていました。
しかし読み返していくうちに、その怖さは「安心」や「信頼」に変わっていきます。アンパンマンは一度も笑いませんが、悲しんでもいません。ひたすらに静かで、誰かのために行動し続けます。そこには「見返りを求めない優しさ」があります。大げさなセリフもなく、ただ困っている人のそばに寄り添い、自分を差し出す。その姿に気づいたとき、怖さよりも温かさが胸に広がるのです。
子どもたちがこの絵本を好きになる理由も、少しわかるようになりました。大人は「顔を食べる=怖い、残酷」と考えますが、子どもは「自分のためにくれた=うれしい、優しい」と受けとります。この感覚の違いこそ、初期アンパンマンの評価を分ける鍵なのだと思います。
初期アンパンマンは、怖さを使って子どもを驚かせるための物語ではありません。怖さを通して「人の悲しみや空腹を想像する力」を育てる物語なのです。
いま読むならこの3冊(1970年代の推し)
初期の怖さや静かな優しさを感じるなら、1970年代に刊行された以下の3冊がおすすめです。いずれもやなせたかし本人の作・絵によるもので、アニメにはない深みが味わえます。
| タイトル | 初版年 | 特徴 |
|---|---|---|
| あんぱんまん | 1973年 | 初登場作。8頭身、人間らしい体つき、顔を差し出す描写が最もストレート。 |
| それいけ!アンパンマン | 1975年 | 体型が3頭身に近づき、少し親しみやすくなるが、献身の姿勢は変わらない。 |
| あんぱんまんとばいきんまん | 1979年 | 初めてばいきんまんが登場。正義と悪の関係性が描かれ始める。 |
特に『あんぱんまん』は、現在のアンパンマン像を作る原点として読む価値があります。そこには、まだ仲間もおもちゃもなく、たった一人で空を飛び続ける孤独なアンパンマンの姿があります。
アニメ・映画が大好きで毎日色んな作品を見ています。その中で自分が良い!と思った作品を多くの人に見てもらいたいです。そのために、その作品のどこが面白いのか、レビューや考察などの記事を書いています。
詳しくはこちら


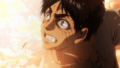
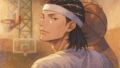
コメント