「鋼の錬金術師」のアニメは、2003年版と2009年版の2つが存在します。
どちらも同じ原作をもとにしていますが、ストーリー展開やキャラクター設定、さらには錬金術やホムンクルスの扱いまで大きく異なります。
そこで本記事では、「ハガレンアニメ 違い」というテーマで、両作品を徹底比較。
初めて観る人はもちろん、原作ファンやリピート視聴を考えている人にも役立つように解説します。
※詳しい作品概要は公式サイトをご覧ください。
ハガレンのアニメ:2003年版と2009年版の基本的な違い
「鋼の錬金術師」のアニメには2003年版と2009年版の2つがあり、それぞれに大きな特徴があります。
両方とも同じ原作をもとにしているのですが、制作時期や原作の進行状況によってストーリーの作り方が大きく変わりました。
ここではまず、それぞれの基本的な違いから見ていきましょう。
2003年版は原作未完のためオリジナル展開
2003年に放送された「鋼の錬金術師」は、当時まだ原作漫画が連載初期だったため、途中からストーリーが追いついてしまうことがわかっていました。
そのため、序盤こそ原作をベースにしながらも、中盤以降は完全にアニメオリジナルの展開となります。
例えば、ホムンクルスの設定やラスボスにあたる存在も原作にはない要素が加えられました。
特に、敵を率いる黒幕として登場した「ダンテ」は完全なアニメ独自のキャラクターで、彼女の存在を軸に後半の展開が大きく変わっていきます。
また、オリジナルキャラクターや原作にない設定が多数盛り込まれており、異世界や魂の門に関する解釈、キャラクターの性格や年齢の改変など、独自の世界観が築かれました。
こうした要素によって、同じ「鋼の錬金術師」でありながら2003年版は原作ファンにとって驚きの連続となり、良くも悪くも「重厚でダークな別物の物語」が展開したのです。
2009年版は原作に忠実なストーリー構成
2009年に放送された「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」は、原作漫画がすでに最終章に突入していたこともあり、全体を通してほぼ原作に忠実な物語展開がなされました。
特に原作ファンにとっては「コミックで読んだあの名シーンがアニメで動いている!」という感動を味わえる構成になっており、例えばグリードとの再会シーンや「約束の日」の決戦などは、原作を知っている人ほど胸が熱くなる場面として高い評価を受けています。
また、最終回も原作の完結とほぼ同じタイミングで放送されたため、連載とアニメが同時にクライマックスを迎えるという稀有な体験を視聴者に与えました。
作品全体を通して原作の物語をアニメでしっかり追体験できることに加え、映像ならではの演出や音楽が加わることで、漫画以上に臨場感を持って物語を楽しめるのが大きな魅力となっています。
制作背景と放送時期の違い
2003年版は「原作の人気に合わせて早期にアニメ化」という流れで制作されました。当時はまだ連載が始まって間もない段階で、アニメの方が先に進んでしまうのは必然だったため、アニメスタッフは最初からオリジナル展開を取り入れる方針を取っていました。
これにより、序盤は原作のエピソードを下敷きにしつつも、次第にアニメ独自の物語が広がっていきます。特に後半は、原作には存在しない「ダンテ」という黒幕キャラクターを中心に物語が展開し、アニメならではの独特の世界観が形作られました。
一方、2009年版は原作の連載終盤に合わせて放送がスタートしたため、最初から最後まで原作に寄り添った物語を描くことが可能でした。全64話という5クールの長期放送が確保されていたこともあり、原作の名シーンや重要なバトルをほとんど漏らすことなく再現できます。
さらに、原作の最終回とほぼ同時期にアニメも最終話を迎えたことで、ファンにとっては「雑誌とアニメの両方で同じクライマックスを体験する」という特別な瞬間になりました。
このように2003年版は原作にない独自の物語を描く必要があり、2009年版は原作に忠実に寄り添った物語を展開するという、大きな方向性の違いが生まれたのです。
ストーリー展開の比較
ここからは、それぞれの作品のストーリー展開の違いを具体的に見ていきます。
両方とも「兄エドワードと弟アルフォンスが、失った身体を取り戻すために旅をする」という軸は同じですが、その描き方は大きく異なります。
序盤の導入とテンポ感の違い
2003年版は序盤からじっくりとキャラクターの心理や事件の背景を描き込む傾向がありました。特にエドやアルが「人体錬成の代償」として苦しむ様子は、何度も彼らの表情やセリフを通して丁寧に描かれ、視聴者はその重さを肌で感じ取ることができます。
母親を蘇らせようとした失敗のシーンも繰り返し言及され、二人が背負う罪と後悔が強調されます。また、サイドストーリー的な回でもそのトラウマが陰を落としており、物語全体の空気は重厚で、観ている側にも深い余韻を残します。
一方、2009年版は序盤からテンポよく進みます。1話ごとに起承転結があるよう意識されており、次回に持ち越さずすっきり終わる回も多いです。そのため視聴者はテンポの良さを感じやすく、子どもでも理解しやすい構成になっています。
例えば「リオールの街」のエピソードでは短い時間で事件の始まりから解決までがまとめられ、物語が停滞せずに前に進む印象を与えます。またシリアスな場面の直後にコミカルな掛け合いが入ることで、緊張が緩和される構成になっており、物語全体を軽快に楽しめる工夫が随所に見られます。
2003年版の重厚でダークな展開
2003年版は「少年漫画らしい冒険活劇」というよりも、社会問題や人間の業を強調したダークな物語が目立ちます。
特に「合成獣(キメラ)」の回では、幼い少女ニーナと犬アレキサンダーが融合させられてしまう悲劇が強烈に描かれ、多くの視聴者に深い衝撃を与えました。
また「イシュヴァール殲滅戦」に関する描写は原作以上に重苦しく、戦争の残酷さや差別の問題が赤裸々に描かれています。その結果、視聴後に胸をえぐられるような感覚を覚えた人も多く、今でも「トラウマになった」と語るファンが少なくありません。
さらに日常のシーンにも陰影が落とされ、音楽や映像演出も重厚さを増すよう工夫されているため、物語全体が強い閉塞感に包まれています。
2009年版の原作準拠でテンポの速い進行
2009年版は原作のエピソードを忠実になぞりながらも、全体のボリュームを64話に収めるために、どうしても駆け足気味に進む部分も目立ちます。
例えば「第五研究所」の戦いは原作同様の展開を踏襲していますが、2003年版と比べるとかなりテンポよく物語が運び、緊迫感が一気に高まる演出になっています。そのためじっくり描写されるシーンは少なくなりますが、逆に視聴者を飽きさせずにテンポよく進行し、ストーリーの流れを止めないという利点があります。
結果として、壮大な原作の物語を最後まできちんと描き切ることができ、連載時に読者が味わったクライマックスをそのままアニメで体感できるという大きなメリットにつながっています。
キャラクター設定の違い
同じキャラクターであっても、2003年版と2009年版では性格や描かれ方が異なることがあります。
これは視聴者に与える印象を大きく変える要素となっています。
エドやアルの性格の変化
2003年版のエドは原作よりも内向的で、苦悩を前面に押し出したキャラクターとして描かれます。小柄な体格を気にして苛立つ場面はあるものの、基本的には自分の罪や失敗を背負い込み、深く思い悩む姿が多く描かれます。
アルもどこか後ろ向きな雰囲気があり、自分が魂だけの存在になったことに戸惑い、兄を支えながらも弱気になる描写が強調されます。全体的に兄弟とも「暗い印象」が強めで、観ている側にも胸が詰まるような重さを感じさせます。
2009年版では原作通り、エドは短気で直情的ながらも根は優しい少年として描かれます。兄としての責任感と子どもらしい無鉄砲さが同居し、失敗しても前を向いて進もうとする姿が際立ちます。アルはおっとりして落ち着いた性格で、兄の暴走をなだめたり、柔らかい言葉で安心感を与える存在です。
兄弟の掛け合いにはしばしばギャグも入り込み、エドの「チビ」ネタに対する怒りやアルの飄々とした受け答えが重苦しさを和らげ、作品全体に温かみとテンポの良さをもたらしています。
登場キャラクター数と扱いの違い
2003年版は登場キャラクターの数が絞られています。特に「シン国」や「北方司令部」のキャラクターは一切登場しません。その代わりにアニメオリジナルのキャラクターが多く登場し、彼らが物語を支える役割を果たしています。
例えば、炭鉱の町で登場するライラや、黒幕として最後まで暗躍するダンテなどは、アニメ独自のキャラクターであり、彼らの存在によって2003年版は原作にはない独特の深みを持ちました。こうしたオリジナルキャラが物語の進行やテーマ性を大きく変化させたのが大きな特徴です。
2009年版は原作キャラクターをほぼ網羅的に登場させるため、非常にキャラ数が多いのが特徴です。シン国のリンやメイ、ブリッグズのオリヴィエなど、原作で人気のあるキャラクターがしっかりと描かれているのはファンにとって嬉しい点です。
ただし、あまり重要でないキャラや物語の流れを大きく変えないキャラについては省略されることもあり、全員が同じ比重で描かれるわけではありません。それでも2009年版は、原作ファンが「このキャラが動いている!」と感じられるほど幅広い人物像を映像化している点で魅力的です。
オリジナルキャラクターと未登場キャラ
2003年版の大きな特徴は、アニメオリジナルキャラの存在です。たとえば物語の黒幕「ダンテ」や、序盤で登場する「ライラ」などは原作には存在しません。
さらに、こうしたキャラクターたちは単なる脇役ではなく、エドやアルの行動や選択に大きな影響を与え、物語全体の方向性を変えていきました。特にダンテは後半の展開を支配する存在として、原作にはない独自の緊張感を作品にもたらしています。
一方ライラは序盤の炭鉱の町で重要な役割を果たし、彼女の存在が後にダンテの正体と結びつくなど、オリジナルならではの伏線の一部にもなりました。
逆に2009年版では、シン国のリンやメイ、ブリッグズのオリヴィエなど原作で人気のあるキャラクターがきちんと描かれています。彼らは原作の名シーンをそのまま再現する形で登場し、それぞれが大きな役割を持って物語を動かします。
特にリンは「グリード」と融合する展開や、オリヴィエはブリッグズの北壁で見せる指導力など、原作の見どころをしっかりと映像化しています。このように、2003年版と2009年版では「原作にいないオリジナルキャラを中心に描いた物語」と「原作キャラを忠実に活躍させた物語」という対比が鮮明に表れているのです。
ホムンクルスの設定の違い
両作品の大きな違いとして語られるのが、ホムンクルスの設定です。
敵キャラクターの核となる存在だけに、ここは非常に重要な違いとなります。
2003年版は「人体錬成の失敗作」
2003年版では、ホムンクルスは「人体錬成の失敗作から生まれる存在」とされています。人間に憧れつつも人間を憎む、という歪んだキャラクター付けがなされ、彼らが抱える苦悩や葛藤が作品全体に影を落としています。
さらに「生前の体の一部」が弱点という設定があり、例えばラストやグラトニーといったキャラクターの倒し方も、原作とは全く異なる独自の演出がなされています。原作を読んでいる人からすると驚きの展開であり、2003年版ならではの衝撃的なクライマックスを形作る要素となりました。
また、ホムンクルスが人間だった頃の記憶や感情を断ち切れずに苦しむ様子が丁寧に描かれることで、ただの敵キャラにとどまらず「悲劇的な存在」としての印象を強めています。
2009年版は「賢者の石を核とした存在」
2009年版では、ホムンクルスは「賢者の石を核として生み出された存在」とされ、原作と同じ設定です。彼らは人間を見下し、自分たちを上位の存在と考える傲慢さを持っています。
致命的な弱点はなく、賢者の石の力で何度も再生しますが、その再生回数には限りがあり、限界を超えると完全に消滅するというルールが設けられています。グラトニーの底知れぬ空腹感や、ラストの妖艶な残虐性など、個々のキャラクター性も原作の描写に忠実に再現されており、視聴者に強烈な印象を与えます。
2009年版では彼らが単なる敵役ではなく、物語全体の構造を動かす重要なピースとして機能しているのが特徴です。
リーダーの違い ― ダンテ vs お父様
2003年版ではホムンクルスを率いるのはアニメオリジナルキャラ「ダンテ」。彼女はかつてホーエンハイムと深い関わりを持っていた存在であり、不老不死を求めてホムンクルスを利用する姿は冷酷そのものです。物語の後半に至るまで暗躍し続け、エドとアルの運命を翻弄します。一方、2009年版では「お父様」と呼ばれる存在がリーダーです。
「お父様」はホーエンハイムと表裏一体ともいえる存在で、世界規模の計画を進める張本人です。その圧倒的な存在感と謎めいた目的が、物語を一気にスケールアップさせ、最終決戦へとつながっていきます。
錬金術描写の違い
錬金術の表現方法や設定にも大きな違いがあります。特に2003年版では原作にない「異世界」設定が追加され、物語に独自の解釈が加えられました。
2003年版の異世界設定と「魂の門」
2003年版では「錬金術の力は異世界から魂を引き出す」という独自設定が登場します。そのため「胸に小さな門を持っている」といった原作にはない表現があり、錬金術師は自分の中に別世界とつながる通路を抱えているような描写が繰り返されました。
この設定は作品全体の雰囲気をより神秘的で不気味なものにし、視聴者に「錬金術とは人間の手に余る危険な力」という印象を強く刻み込みます。さらに異世界は私たちの住む現実世界によく似た場所として描かれ、戦争や科学技術が存在する点でもパラレルワールド的な立ち位置を持っています。
終盤ではエドがその異世界にたどり着き、機械工学や飛行機などが登場することで、これまでの物語の前提が大きく揺さぶられる驚きの展開につながります。この「異世界」と「魂の門」の設定は、2003年版ならではの最大の特徴であり、原作にはない解釈を大胆に盛り込むことで視聴者に強烈な印象を与えたのです。
2009年版は原作と同じ錬金術ルール
2009年版では原作通り「等価交換」のルールに基づき、錬金術が描かれます。異世界設定は存在せず、あくまでこの世界の理として錬金術が機能しており、その背景には「お父様」と呼ばれる存在が深く関わっています。
物語が進むにつれて、国家規模の錬成陣や「約束の日」と呼ばれる計画の全貌が明らかになり、錬金術そのものの秘密が徐々に紐解かれていくのです。こうした展開は原作と同じ流れをたどっており、特に大地そのものを使った巨大な錬成や、人柱として選ばれた人々の存在などはスケール感を大きく広げています。
また、「等価交換」のルールを貫いた物語の結末は、キャラクターたちの選択や犠牲に重みを持たせる重要な要素となっています。原作ファンにとっては、細部まで違和感なく物語に没入できるだけでなく、原作を読んでいない視聴者にとっても筋が通った世界観として自然に受け入れられる作りになっているのです。
光やエフェクト表現の違い
また、錬金術を発動するときの光も大きな違いとして挙げられます。2003年版では黄色の光で描かれることが多く、どこか暖かみや不気味さを併せ持った演出になっていました。
対して2009年版では、通常の錬成は青色、賢者の石を使った場合は赤色と、明確に色分けがなされています。青は冷たさや理性的な印象を与え、赤は強大で危険な力を象徴するため、物語の緊張感や緩急を際立たせる効果がありました。
さらに発光の仕方やエフェクトの細部も異なっており、2003年版は柔らかくにじむような光が多いのに対し、2009年版は鋭い線と派手な閃光が強調される傾向があります。こうした映像的な演出の違いは、同じ錬金術のシーンでもまったく異なる印象を視聴者に与え、それぞれの作品の世界観を形作る重要な要素となっています。
作品全体の雰囲気とテーマ性
両作品は「兄弟の絆」「人間の業」というテーマは共通していますが、作品全体の雰囲気は大きく異なります。
2003年版は鬱展開とトラウマ級の描写
2003年版は全体的に重苦しく、トラウマ級のエピソードも少なくありません。特にニーナとアレキサンダーのキメラ回や、ヒューズ中佐の悲劇的なシーンは、多くの視聴者に強烈な印象を残しました。
そのほかにも、マルコー博士の研究や軍の陰謀が描かれる場面、イシュヴァール戦争の描写などは、戦争や差別の残酷さを突きつけるものとして強い衝撃を与えました。
日常回でさえも暗い影を落とすような演出が多く、音楽も重厚で哀愁を帯びたものが選ばれているため、作品全体の空気は常に緊張感に包まれています。
視聴者の心に深く突き刺さるシーンが連続し、見終えた後もしばらく重さが残るような体験をもたらしました。
2009年版はギャグも交えた少年漫画的演出
2009年版は原作通り、重い展開の合間にコミカルなシーンを挟みます。エドが「ちっちゃい」ネタで怒ったり、アルが兄をなだめたりする掛け合いが、物語全体のバランスを保っています。
さらに、ホークアイ中尉とロイの軽妙なやり取りや、リンとグリードのユーモラスな掛け合いなど、シリアスとギャグの切り替えがテンポよく行われる点も特徴です。
これにより物語の深刻さが際立つ一方で、視聴者が気持ちを和らげる瞬間もきちんと用意されています。
そのため子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる内容になっており、シリアスとユーモアのバランスが絶妙な作品として親しまれています。
声優・スタッフ陣の違い
制作スタッフや声優陣にも違いがあります。
ただし、エルリック兄弟の声優は続投しており、視聴者にとって馴染みやすい部分も残されています。
エルリック兄弟の声優は続投
| キャラクター | 2003年版 | 2009年版 |
|---|---|---|
| エドワード・エルリック | 朴璐美 | 朴璐美 |
| アルフォンス・エルリック | 釘宮理恵 | 釘宮理恵 |
兄弟役の声優が変わらなかったことは、作品が変わってもキャラの一貫性を感じられる大きなポイントです。
その他のキャストとスタッフの入れ替わり
2003年版と2009年版では、多くの脇役キャラの声優が変更されました。例えばロイ・マスタングやリザ・ホークアイといった人気キャラも担当声優が一新されており、それぞれの人物像に新しい解釈や個性が加わっています。
そのため、同じキャラクターでも声の響きや感情の表現が異なり、視聴者に与える印象は大きく変わりました。
さらに監督や脚本といった主要スタッフも大きく入れ替わっており、演出の方向性や作品全体のトーンそのものが刷新されました。
2003年版は水島精二監督の下でシリアスかつ重厚な物語性を重視した演出が際立ち、音楽や色彩設計もその雰囲気を支えるように作られています。一方で2009年版は入江泰浩監督が手がけ、よりテンポの速い展開と原作準拠の構成を取り入れたことで、明るさと勢いが感じられる仕上がりとなっています。
こうした声優とスタッフの大幅な変更が相まって、作品全体の演出方針や空気感はまったく異なるものとなり、それぞれに独自の魅力を生み出す要因となったのです。
音楽と主題歌の違い
「ハガレン」といえば、主題歌のクオリティの高さも語り草になっています。
2003年版と2009年版では音楽の方向性も異なり、それぞれに名曲が生まれました。
2003年版の重厚な楽曲ラインナップ
2003年版ではポルノグラフィティの「メリッサ」、L’Arc〜en〜Cielの「READY STEADY GO」などが主題歌となり、アニメブームを支える存在になりました。これらの楽曲は放送当時の若い世代に強烈な印象を残し、今でもカラオケで歌われる人気曲となっています。
エンディングも北出菜奈の「消せない罪」やCrystal Kayの「Motherland」など、多彩なアーティストが参加し、作品の重厚な雰囲気を音楽で支えていました。楽曲のテイストもバラードからロックまで幅広く、各話のシリアスな展開をさらに引き立てる役割を果たしました。
特に「リライト」は作品後半を象徴する力強さを持ち、ファンの間で語り継がれる名曲となっています。
2009年版の勢いある主題歌群
2009年版ではYUIの「again」、シドの「嘘」、スキマスイッチの「ゴールデンタイムラバー」など、時代を彩るアーティストが勢揃いしました。
これらの楽曲は作品の明るさや疾走感を前面に押し出し、2003年版とはまた違った魅力を演出しています。
特にYUIの「again」は第1話から視聴者の心を掴み、シリーズ全体の幕開けを盛大に飾りました。「嘘」は静かな切なさを伴い、物語の転換期に深い余韻を残す曲として親しまれています。
さらに「Period」や「レイン」は、物語終盤を盛り上げる楽曲として多くのファンに愛され、放送当時の感動を思い出させる象徴的な存在になっています。
オープニングとエンディングを通じて、2009年版はテンポ感と勢いを重視した構成になっており、楽曲そのものが作品の雰囲気作りに大きく貢献していました。
まとめ ― どちらを観るべき?
最後に、視聴者が気になる「どちらを観るべきか」という点をまとめます。
原作ファンには2009年版がオススメ
原作漫画を忠実に楽しみたい方には2009年版が断然おすすめです。キャラクターの登場もほぼ原作通りで、物語を最後まで追えるので、原作のファンであれば満足度は非常に高いでしょう。
特に、原作の名シーンがそのまま動くアニメーションとして体感できるのは大きな魅力です。例えば「約束の日」の大決戦や、グリードやホーエンハイムとの重要なエピソードは迫力ある映像と音楽で再現され、漫画では味わえない臨場感を与えてくれます。
また、原作の最終回と同時期に放送が完結したため、リアルタイムで追っていたファンにとっては一生に一度の特別な体験となったでしょう。こうした忠実さと映像ならではの演出が合わさることで、2009年版は「原作を最大限に楽しむためのベストな手段」と言えるのです。
重厚なオリジナルストーリーを味わいたいなら2003年版
一方で、2003年版のオリジナル要素や独自の重厚な物語が好きというファンも多いです。原作では描かれなかった展開を体験したい方や、シリアスでダークな雰囲気を好む方には2003年版がおすすめです。例えば黒幕「ダンテ」の存在や、ホムンクルスの出生設定などはアニメ独自の要素で、視聴者に衝撃を与えました。
物語の後半は原作とは大きく異なる方向に進み、予想外の展開や登場人物たちの悲劇的な結末が強烈に印象に残ります。重苦しくも人間の業を描いたこの世界観は、原作に忠実な2009年版とは対照的であり、「もう一つのハガレン」として多くのファンに深く支持されています。
両方の作品に良さがあり、好みによっておすすめは変わります。迷っている方は、まず2009年版で原作の物語をしっかり味わい、その後に2003年版を観て「もう一つのハガレン」を楽しむのが一番贅沢な楽しみ方かもしれません。
アニメ・映画が大好きで毎日色んな作品を見ています。その中で自分が良い!と思った作品を多くの人に見てもらいたいです。そのために、その作品のどこが面白いのか、レビューや考察などの記事を書いています。
詳しくはこちら



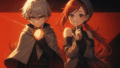
コメント